法務省が動き出した背景
法務省展開調查的背景
2026年度、法務省は「ヘイトスピーチ」に関する大規模な実態調査に乗り出す方針を固めました。差別をあおる言動や排外的なメッセージは、もはや一部の街頭デモにとどまらず、SNSやネット掲示板といったオンライン空間で日常的に目にするものとなっています。特に、誰もがスマートフォンで簡単に発信できる時代になったことで、差別的な投稿が拡散しやすくなり、社会に与える影響も大きくなりました。法務省が今回の調査に踏み切るのは、こうした社会状況の変化を正確に捉え、対策を検討する必要があるからです。
国内でヘイトスピーチが社会問題として強く認識されるようになったのは2010年代のことです。一部の団体が街頭で在日コリアンに対する差別的な言葉を叫び、時に暴力を示唆する行動も見られました。これらは大きな社会的反発を呼び、国会でも繰り返し議論が行われました。その結果、2016年には「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、理念として「差別的言動をなくすべきである」という方向性が示されました。しかし、この法律には直接的な罰則規定はなく、実効性については常に議論が続いています。
今回の調査は、2026年6月で解消法の施行から10年を迎えるという節目にあたることも大きな要因です。制度の成果と課題を洗い出し、今後の法制度や政策の見直しにつなげるために、現状を把握することが欠かせないのです。
2026年度,日本法務省決定展開一項關於「仇恨言論」的大規模實態調查。煽動歧視或排外的訊息,不再僅限於街頭示威,而是在SNS與網路論壇上隨處可見。特別是在人人都能以手機輕易發聲的時代,歧視性言論的擴散更快,對社會影響也更深。法務省推動此次調查,是為了準確掌握這種社會變化並研擬對策。
日本社會將仇恨言論視為重大問題,是在2010年代。一些團體在街頭針對在日韓國人高喊歧視性言語,有時甚至暗示暴力。這些行為引發社會強烈反彈,國會多次討論。最終在2016年通過了《解消仇恨言論法》,確立了「應該消除歧視性言行」的理念。但該法律並未設置直接罰則,因此其實效性一直受到爭議。
此次調查還因為2026年6月正值該法律施行滿十週年。為了檢視制度成效與問題,並推動法制或政策檢討,掌握現狀是不可或缺的。
SNSで広がる差別と言動の多様化
在SNS中擴散的歧視與言行多樣化
近年の特徴は、差別の舞台が街頭からインターネットへと移ったことです。街頭デモは以前よりも減少傾向にある一方、匿名性が高く拡散力を持つSNSや掲示板では、差別的な書き込みが目立つようになりました。インターネット上の発言は、短時間で多くの人に届くため、一度投稿されると消し去ることが難しく、被害が拡大しやすいという課題があります。
さらに、対象となる人々も多様化しています。これまで特に大きな問題とされてきたのは在日コリアンへの差別ですが、近年ではクルド人など、特定地域に居住する外国人コミュニティが新たにターゲットとされる事例も確認されています。地域社会に根付いて暮らしている人々が、根拠のない不安や偏見から差別的な言葉を浴びせられる状況は、共生社会の実現を大きく阻む要因となっています。
法務省は、こうした現状を把握するために約7,000万円の調査費用を予算に計上しました。調査では、どのような差別的言動が、どの媒体で、どの程度発生しているのかを明らかにすることが期待されています。これにより、現状の課題を可視化し、効果的な対策につなげることができます。
近年的特徵,是歧視的舞台已從街頭轉移至網路。雖然街頭示威減少,但匿名性強、擴散力大的SNS與論壇上,歧視性言論卻更加顯眼。這些發言能在短時間內觸及大量群眾,一旦發布就難以完全刪除,使受害擴大。
此外,受害對象也趨於多樣化。過去最受關注的是針對在日韓國人的歧視,但近年來,庫德人等特定地區的移民社群也成為新目標。這些深耕於地方社會的居民,因無根據的恐懼或偏見而遭受歧視,對「共生社會」的實現造成嚴重阻礙。
法務省因此在預算中列入約七千萬日圓作為調查經費。調查將釐清「哪些歧視言行、在哪些媒體、發生頻率如何」,以便可視化問題並推動有效對策。
調査の目的と意義
調查的目的與意義
今回の調査の目的は単なる数値の収集ではありません。第一に、現状を科学的に把握することで、これまでの政策や法律がどの程度有効だったのかを検証する役割を持ちます。街頭デモが減ったのは法整備や社会的批判の成果なのか、それとも活動の場が単にオンラインへと移っただけなのか。その実態を明らかにしなければ、対策の方向性を誤ってしまいます。
第二に、対象が多様化している現状に対応するためです。在日コリアンに加え、クルド人やその他の外国人コミュニティも差別の矢面に立たされており、それぞれの実情を把握することが不可欠です。どのような人々が被害を受けているのかを可視化することで、支援の仕組みをより具体的に整えることが可能になります。
第三に、調査は政策や制度の見直しに直結します。ヘイトスピーチ解消法には罰則がないため、実効性を高めるには別の仕組みが必要ではないかという議論があります。調査結果を踏まえ、必要なら新たな法改正や規制強化、教育啓発の強化が検討されることになるでしょう。さらに、被害者が安心して相談できる体制をどのように整備するかも課題です。
そして最後に、この調査そのものが社会への強いメッセージとなります。国が公式に「差別的言動は問題である」と明言することで、抑止力が働き、社会全体に啓発効果を及ぼすのです。外国人住民だけでなく、日本社会全体が差別にどう向き合うのか、その姿勢を示す象徴的な取り組みといえるでしょう。
此次調查的目的並非單純蒐集數據。首先,透過科學方式掌握現況,可以檢驗既有政策或法律的有效性。街頭示威的減少,是因為制度奏效,還是僅僅轉移到網路?若不釐清實態,對策方向可能會誤判。
其次,為應對受害對象的多樣化。在日韓國人之外,庫德人與其他移民社群也遭受歧視,必須了解其實際情況。透過可視化,才能設計出更具體的支援機制。
第三,調查將直接影響政策檢討。《解消仇恨言論法》缺乏罰則,若要提高實效性,可能需要新法修訂、規制強化或加強教育宣導。此外,如何建立讓受害者安心諮詢的支援體系,也是未來挑戰。
最後,這項調查本身就是對社會的明確訊號。國家正式表明「歧視性言行不可接受」,不僅具有嚇阻效果,也能提升社會大眾的意識。這是日本社會面對歧視問題的一項象徵性行動。
これからの課題と私たちにできること
未來的課題與我們能做的事
ヘイトスピーチの実態調査は大切な一歩ですが、調査だけで差別がなくなるわけではありません。むしろ、調査によって問題の大きさや多様性が改めて浮き彫りになれば、社会としてどのように対応していくかがより重要になります。
まず課題となるのは、インターネット上での差別発言をどのように扱うかです。表現の自由との兼ね合いもあり、単純に規制すればよいという問題ではありません。プラットフォーム事業者との協力、違法性の高い投稿の削除要請、啓発活動による発信者意識の向上など、多方面からの取り組みが求められます。
また、差別を受けた人々が安心して相談できる窓口や支援体制の充実も不可欠です。心理的な負担を軽減するサポートや、法的な対応の仕組みを整えることで、被害者が孤立しない社会をつくることができます。行政だけでなく、地域社会やNPO、専門家が連携して取り組むことが必要でしょう。
そして何より、私たち一人ひとりが差別に対して無関心でいないことが大切です。SNSで差別的な発言を目にしたときにどう向き合うのか、偏見に基づく情報をうのみにせず、正しく理解する努力をするのか。日常の小さな選択が、社会全体の空気を変えていきます。
2026年度に予定されている調査は、日本社会が次の10年をどう歩むかを考えるための出発点です。差別をなくし、多様な人々が共に生きられる社会をつくるために、行政の取り組みだけでなく、市民一人ひとりの意識が問われています。
仇恨言論的實態調查是一個重要的起點,但調查本身並不會讓歧視消失。相反,調查若揭示了問題的嚴重性與多樣性,社會該如何因應才是更大的課題。
首要課題是如何處理網路上的歧視性發言。這涉及表達自由,不可能單靠規制解決。需要平台業者配合,對高違法性的貼文提出刪除要求,並透過教育宣導提升發言者的意識,多管齊下。
其次,必須強化受害者的支援體系。提供心理輔導、法律協助,讓他們不再孤立無援。這需要政府、社區、NPO與專業人士合作推動。
最重要的是,每個人都不能對歧視無動於衷。當我們在SNS看到歧視言論時,如何回應?能否避免盲目相信偏見訊息,並努力理解真相?日常中的小小選擇,將逐漸改變整個社會氛圍。
2026年度的調查,是日本社會思考未來十年的起點。為了建構一個沒有歧視、人人共生的社會,不僅需要政府的努力,更需要市民的共同意識。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
「这种事情也能咨询吗?」
—— 没关系!我们会细心倾听并解决您的不安
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
在富士行政书士事务所,我们致力于帮助在日本生活的外国人安心地度过每一天。不仅仅是签证问题,对于手续、工作、生活中遇到的不安和烦恼,我们也会用心陪伴。
“我不知道该向谁咨询”,正是在这种时候,请联系我们。
我们会和您一起找到最合适的解决方式。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
※如果您未使用LINE,也可以通过▶ 联系表单 与我们沟通。
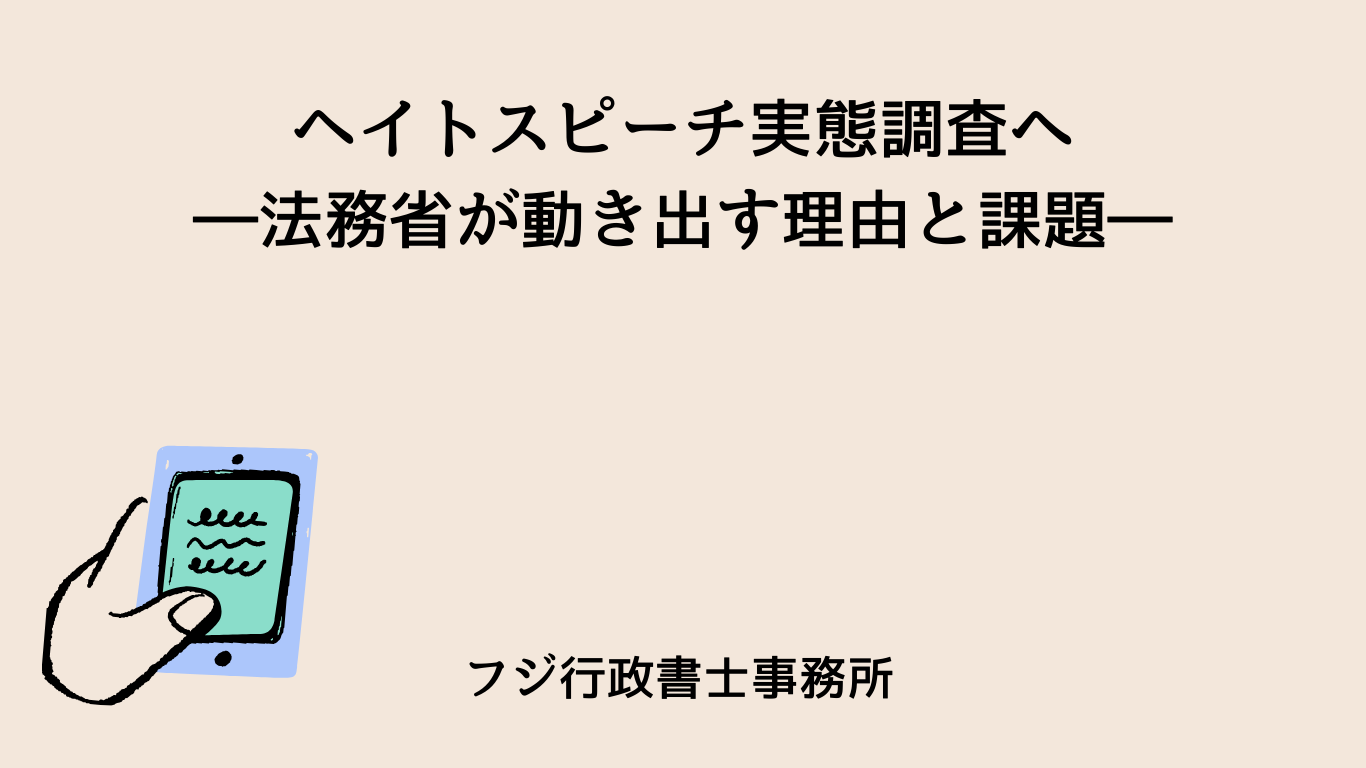
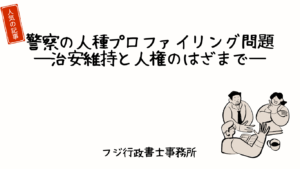
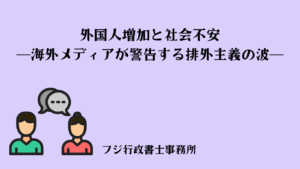

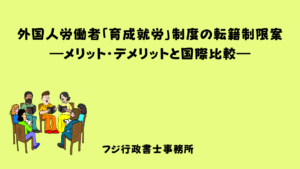

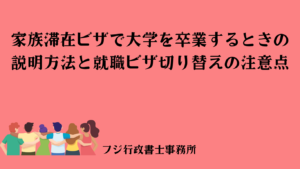
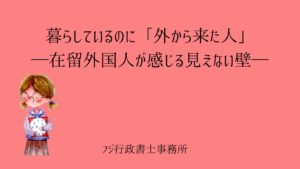
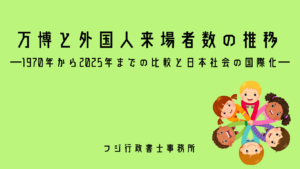
コメント