技人国の本来の趣旨と派遣労働の広がり
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、日本で外国人が高度な知識や技能を活かして働くために設けられた制度です。大学や専門学校を卒業し、一定の専門性を有することが条件とされ、通訳や翻訳、システムエンジニア、貿易実務、会計、人事などの専門職が対象になります。つまり、現場作業や単純労働は対象外であり、制度の根本理念は「高度人材の受け入れ」です。
しかし現実には、この技人国の資格を持つ外国人が派遣労働という形で働く事例が増えています。2024年末時点で技人国の在留者数は約41万人に達し、過去最多を更新しました。そのうち約4万人、つまり一割程度が派遣契約を結んでいると入管庁は把握しています。これは単なる一部の事例ではなく、制度の利用の一形態として定着しつつあることを示しています。
派遣が広がる背景には、日本社会の人手不足があります。特に中小企業では外国人を直接雇用する余裕がなく、派遣会社に依存して労働力を確保する傾向が強いのです。派遣を利用すれば採用や教育にかかるコストを削減でき、必要な時に人材を投入できるというメリットがあります。外国人本人にとっても、就職活動の手間を省き、卒業後すぐにビザを維持できる安心感があるため、派遣は一見便利な選択肢に見えます。こうした双方の利害の一致が、派遣を通じた就労を後押ししているのです。
しかし、その仕組みは大きな矛盾を抱えています。派遣先で従事している業務内容が、入管法で規定された専門的・技術的な業務に該当しないことが多いのです。申請上は「通訳」や「設計補助」とされていても、実際には工場ラインでの単純作業、倉庫での仕分け、飲食店での調理補助などに従事しているケースがあります。この「建前と実態の乖離」が、技人国制度の信頼性を揺るがしているのです。
派遣をめぐるトラブルの実態
派遣労働を通じた技人国就労には、数多くのトラブルが生じています。代表的なのは「資格外活動」です。技人国の資格は専門的な業務を前提としており、現場作業や単純労働は含まれません。にもかかわらず派遣先でそうした業務を担えば資格外活動となり、外国人本人は在留資格取消しや退去強制のリスクを負います。派遣会社や企業にとっては一時的な労働力確保にすぎませんが、外国人本人にとっては生活基盤を失う深刻な問題になります。
さらに、賃金未払い・低賃金も深刻です。派遣会社がマージンを差し引き、本人に最低賃金すれすれ、あるいはそれを下回る報酬しか渡さない事例があります。言語の壁や法律知識の不足により、外国人が不当な扱いを受けても泣き寝入りせざるを得ないケースが多発しています。実際、行政の労働相談窓口やNPOには、未払い残業代、過重労働、雇止めに関する相談が相次いでいます。
また、派遣労働特有の構造的な問題として「責任の所在」が不明確です。雇用契約の主体は派遣会社ですが、実際の指揮命令は派遣先企業が行います。この二重構造のため、トラブル発生時に「どちらが責任を負うか」が曖昧になり、問題が長期化するのです。例えば労災や不当解雇などのケースでは、派遣会社と派遣先の双方が責任を回避し、当事者である外国人が取り残されることが少なくありません。
報道された摘発事例もあります。老舗和菓子メーカーが中国人を工場に入れて包装や仕分けをさせたケース、横浜の飲食チェーンが中国人を厨房業務に就かせていたケースなどです。いずれも申請上は専門業務とされていたものの、実態は単純作業であったため、不正就労として摘発されました。また、行政書士の調査によれば、派遣会社が「本人用」と「入管用」の二種類の契約書を用意し、虚偽の業務内容を記載して在留資格を取得する「二重契約」の実態も存在するといいます。これらは制度の根本を揺るがす重大な問題です。
入管庁の対応と制度見直しの動き
こうした問題の深刻化を受け、出入国在留管理庁は技人国の派遣労働に関する実態調査に乗り出しました。派遣先で単純作業を担わせるケースが確認されており、是正が必要と判断されたためです。今後、入管庁は有識者会議を開催し、具体的な対応策を議論する予定です。
検討されている対策には、まず派遣契約に関する報告制度の導入が挙げられます。派遣元と派遣先の契約内容を定期的に入管に提出させ、業務内容が適切かどうかを監視する方法です。次に、現場調査や本人へのヒアリングを通じた業務内容の確認強化があります。さらに、悪質な派遣会社に対しては行政処分や許可取消しといった厳しい措置を講じる案も検討されています。これにより制度の抑止力を高め、不正利用を防ぐ狙いです。
同時に、起業向け在留資格「経営・管理」の要件厳格化も検討対象となっています。資本金や事務所要件を形式的に整えただけのペーパーカンパニーによるビザ取得が問題となっており、こちらも制度改正が進められる可能性があります。つまり、外国人の就労全般について「建前と実態の乖離」を解消する方向に制度が動き始めているのです。
今後の展望と社会への影響
技人国をめぐる派遣問題は、日本社会全体に広く影響を及ぼす重要なテーマです。第一に制度の信頼性の問題があります。形式と実態の乖離が放置されれば、外国人も企業も「正しく申請しても現場は違反だらけ」という不信感を抱き、優秀な人材の獲得競争において日本が不利になる恐れがあります。
第二に、外国人本人のキャリア形成への影響があります。派遣先で単純作業をしてしまえば、母国帰国後に専門的職歴として評価されず、本人が望んだキャリアパスが断たれてしまいます。せっかく日本で得た経験が逆に不利益となる危険性もあります。これは外国人個人だけでなく、日本の国際的信用にも関わる問題です。
第三に、社会統合への悪影響も懸念されます。外国人が低賃金・不安定雇用に固定されれば、日本人との格差が拡大し、地域社会での摩擦を生む要因となります。共生社会を掲げる以上、このような構造的な不公平は放置できません。
今後求められるのは、制度と現場実態の一致を図ることです。入管庁の監視強化に加え、企業が制度趣旨を理解し責任を持って外国人を雇用する姿勢が必要です。外国人自身が自らの権利を理解し、不当な条件に声を上げられる仕組みも整えるべきです。そのためには行政書士や弁護士といった専門家の役割も大きく、適正な申請と労務環境の確保に積極的に関与することが期待されます。
「技人国で派遣」という矛盾は、日本が国際化と人手不足のはざまで直面している現実を映し出しています。本来は専門性を持つ外国人を受け入れるための制度が、実際には安価な労働力確保の手段として利用されているのです。ここには制度設計の甘さ、現場の苦境、そして外国人本人の生活事情が交錯しています。入管庁が動き始めた今、日本はこの問題に真剣に向き合う必要があります。外国人も日本人も納得できる就労環境と社会の信頼を築けるかどうか。その成否はこれから数年の取り組みにかかっているのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
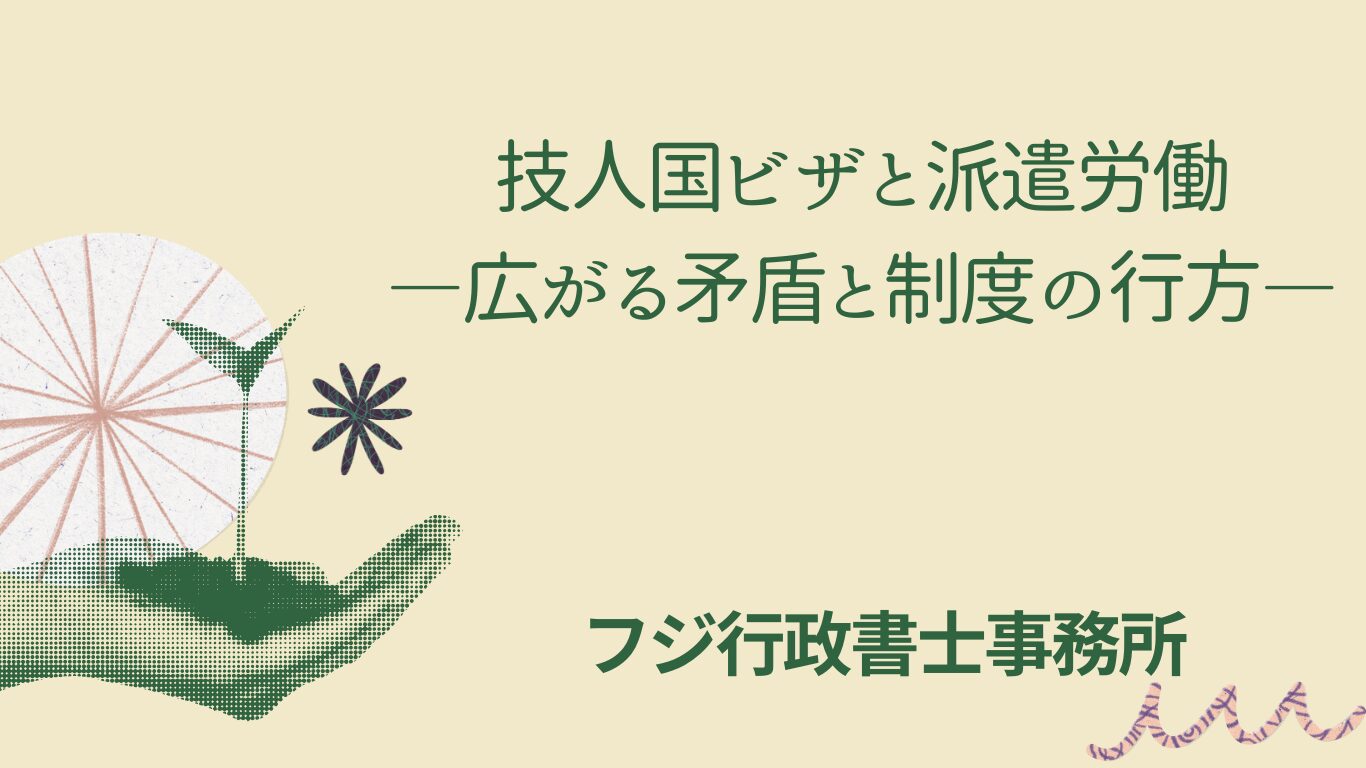

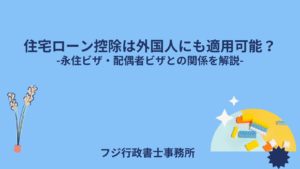
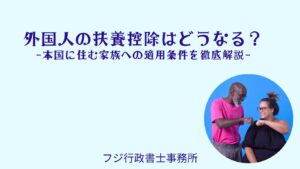
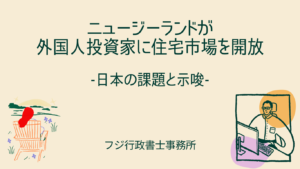
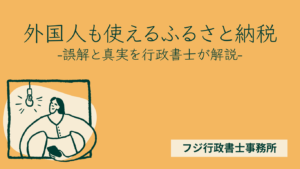
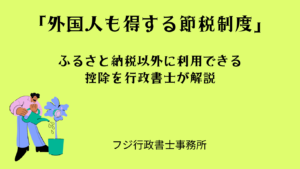
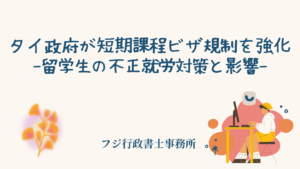
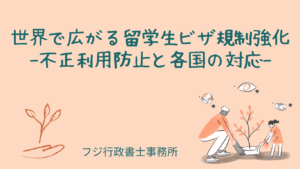
コメント