日本への入国を阻む「COE不許可」という現実
外国人が日本で暮らし始めるためには、まず「在留資格」を得る必要があります。これはいわゆるビザに該当するもので、就労や留学、結婚、家族との同居など、目的に応じた種類があります。そして、それを取得するための最初の関門が「在留資格認定証明書(COE)」の申請です。
COEとは、日本の入国管理局が発行する証明書で、申請者の活動内容が法令上の在留資格に該当し、その条件を満たしていることを事前に確認する制度です。海外にいる外国人が日本の大使館や領事館でビザを申請する際、このCOEを提出することで、審査が迅速かつ確実に進められるようになります。
しかし、このCOEが「不交付」となるケースも少なくありません。申請したにもかかわらず、入管から「認定できない」と通知されると、当然ながら日本に入国することはできません。その理由が通知書に詳しく書かれているわけでもなく、なぜ不許可になったのか、どこに問題があったのか分からないまま戸惑う申請者も多いのが現状です。
この記事では、在留資格認定証明書が不許可(不交付)となる主な理由と、再申請に向けてどのような対応が必要なのかについて、実務的な視点から詳しく解説していきます。
なぜ「不許可」になるのか──主な原因と審査の観点
在留資格認定証明書が不交付となる理由は一つではなく、さまざまな観点から総合的に判断されます。以下に、実務上よく見られる不許可理由を紹介します。
まず、最も多いのは「提出書類の信頼性に疑義がある場合」です。たとえば、学歴や職歴に虚偽があったり、提出された資料の内容に矛盾があったりすると、「信用できない申請」として認定されにくくなります。また、過去の申請と大きく内容が食い違っている場合も、審査官は不自然さを感じるでしょう。
次に、申請者本人が「在留資格の基準を満たしていない」と判断されるケースがあります。就労ビザの場合、学歴や職務内容、実務経験が求められます。大学を卒業していない、あるいは専攻と職種がかけ離れていると、審査で落とされる原因となります。結婚ビザの場合には、交際の実態や結婚の真実性が重視されますが、出会いや交際期間の説明が曖昧だと「偽装結婚」の疑いを持たれることもあります。
また、経済的な基盤に不安がある場合も不交付につながります。留学ビザであれば、学費や生活費を誰がどう負担するのかが問われます。資金提供者の収入証明や送金能力の裏付けが不足していると、「安定した生活が見込めない」として認定されません。就労ビザでも、雇用先企業が赤字続きだったり、設立直後で実績がない場合は、「継続的な雇用が見込めない」と判断される可能性があります。
さらに、申請者や受け入れ機関に過去の問題がある場合も注意が必要です。以前にオーバーステイしていた、退去強制歴がある、刑罰を受けた経歴があるといった場合には、原則として不許可になると考えておくべきです。企業や学校の側に過去の不正受け入れ歴がある場合も、申請者個人に責任がなくても審査に悪影響を及ぼすことがあります。
通知書には書かれていない「本当の理由」をどう探るか
在留資格認定証明書が不交付になると、申請者には入管から通知書が届きます。ところが、その通知には「在留資格該当性が認められなかったため」や「必要な立証が不十分だったため」といった、非常に抽象的な文言しか記載されていません。これでは「どこに問題があったのか」「何を直せばよいのか」が分からず、再申請の準備すらままなりません。
そこで重要になるのが、入管窓口での聞き取り対応です。不交付通知を受け取ったら、できるだけ早い段階で入国管理局の窓口に出向き、担当者に事情を尋ねることが必要です。ただし、ここにもいくつかの注意点があります。
まず、窓口に行けば誰でもすぐに話を聞いてもらえるわけではありません。担当官が不在のことも多いため、事前に電話でアポイントを取るのが賢明です。また、担当官は審査の方針や理由について、詳細に説明してくれるわけではありません。基本的には「制度の範囲内」での応答にとどまり、個別の対策や改善点を教えてくれることはありません。
そのため、聞き取りではこちらから積極的に質問を投げかけ、ヒントを探る姿勢が求められます。「活動内容が在留資格の範囲に当たらなかったということでしょうか」「提出書類に不足があったでしょうか」といった問いかけを通じて、審査でどこに疑義が持たれたのかを探り出すのです。
このような対応が不安な場合は、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの手です。行政書士は入管実務に通じており、職員の発言の意図を正確に把握したり、次の申請で必要となる補強資料を助言したりすることができます。専門家のサポートがあれば、再申請に向けた準備もより確実に進めることができるでしょう。
再申請は可能だが、「解消すべき課題」が明確であることが条件
COEが不交付となっても、再申請は可能です。制度上、申請の回数や期間に制限はなく、問題が解消されていれば何度でもチャレンジすることができます。
ただし、一度不交付となった申請は、次回以降の審査がより厳しくなるのが現実です。入管側は「前回不許可となった理由をどのように改善したのか」を特に注視します。そのため、前回とほぼ同じ書類内容で提出した場合は、当然ながら再び不許可になる可能性が高くなります。
再申請にあたっては、まず聞き取りで把握した問題点をすべて解消することが大前提です。たとえば、資金面での不安が原因だった場合には、通帳残高や収入証明書を補強し、送金者との関係性を明確にする必要があります。活動内容の要件不一致が疑われた場合には、業務内容説明書や会社の事業内容資料を充実させ、在留資格との整合性を明示する工夫が求められます。
ただし、どれだけ努力しても再申請が認められないケースも存在します。たとえば、意図的な虚偽申請があった場合や、過去に重大な在留違反があった場合は、入管からの信頼を大きく損なっており、簡単には覆せません。このようなケースでは、経緯を正直に説明し、反省文などを添付して誠意を示すしかない場合もあります。
いずれにしても、再申請は「やり直し」ではなく「修正・補強を加えた新たな申請」でなければなりません。前回の不許可を踏まえて、具体的にどこを改善し、どのような立証資料を添えるのか。その準備を丁寧に行うことが、再びチャンスを得るための鍵となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
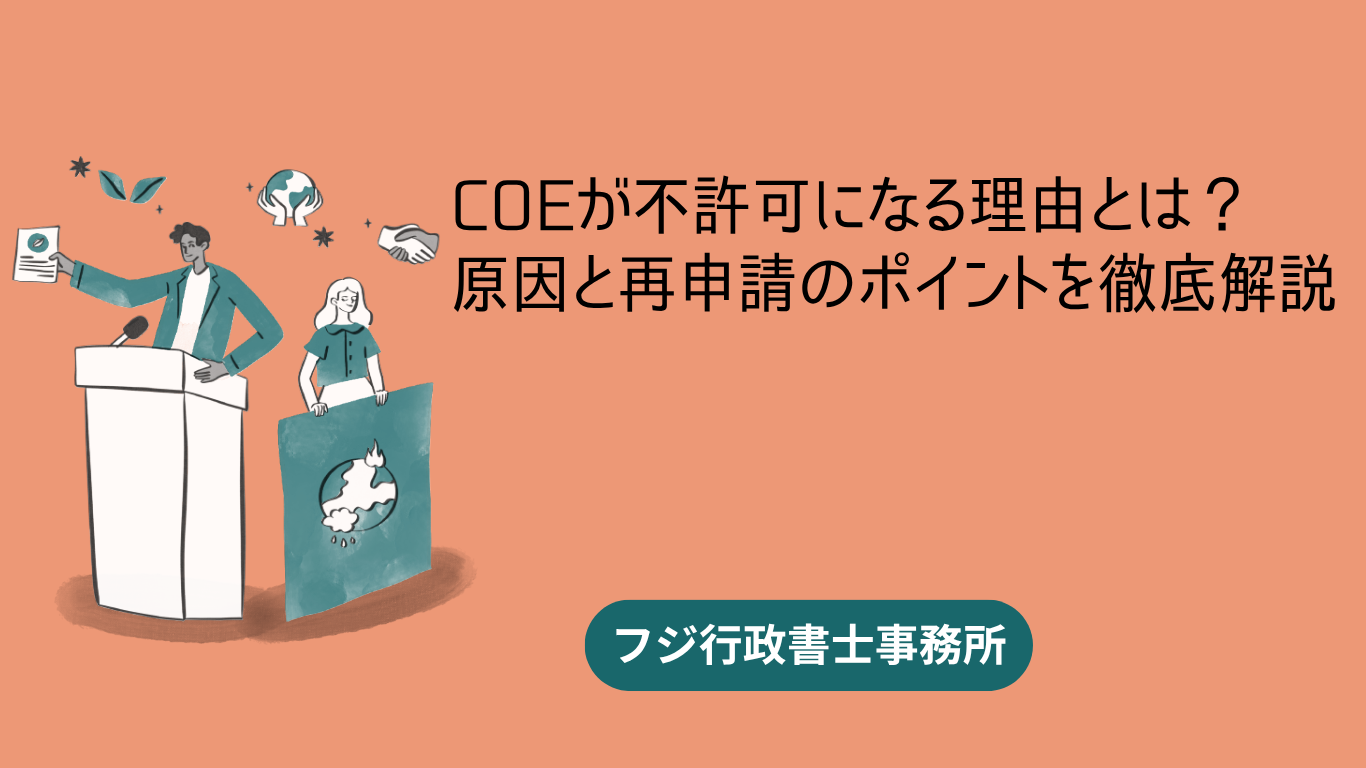
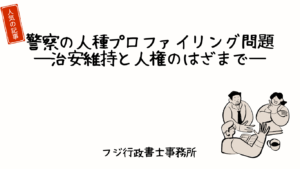
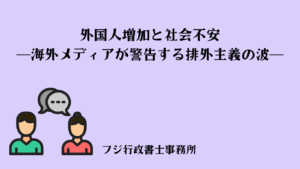

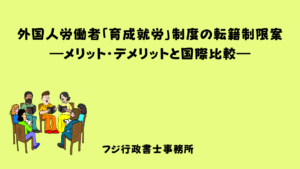

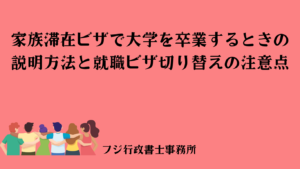
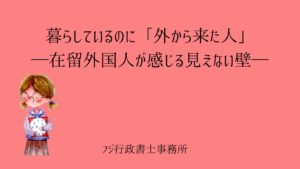
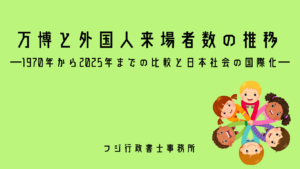
コメント