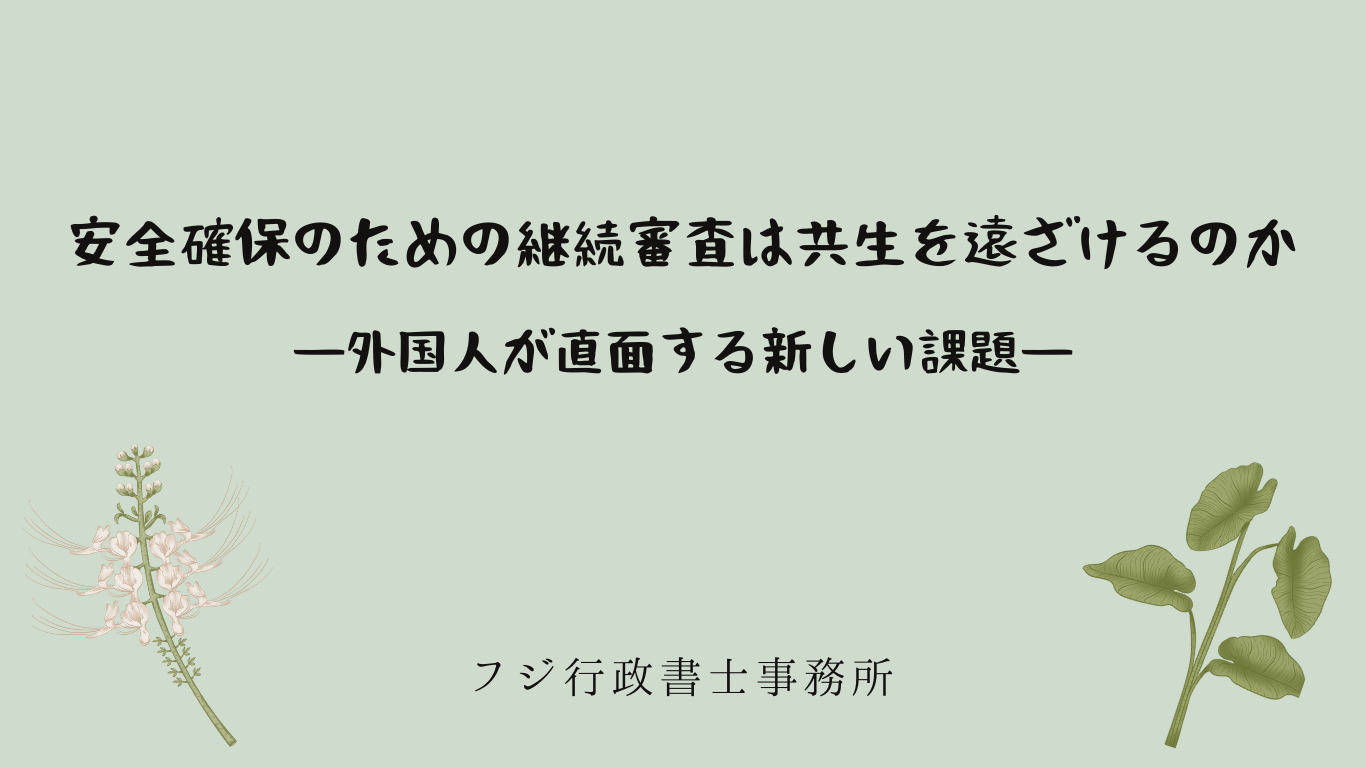安全確保としての継続審査の意義
外国人の受け入れは国の発展や国際交流に不可欠な要素ですが、その一方で治安維持や社会秩序の確保という課題を常に抱えています。アメリカで導入された「継続的審査」は、この二つの課題に応える新しい仕組みとして注目されています。ビザを取得した段階で一度きりの審査を終えるのではなく、滞在中も継続的に行動や生活状況を確認し、入国や滞在の条件を守っているかを見極める。この制度は一見すると厳格すぎるように感じられるかもしれませんが、安全確保の観点からは合理的だといえます。
犯罪行為やテロ行為に結びつくリスクは、入国時点では顕在化していないことも多く、滞在中に発生するケースも少なくありません。例えば、入国後に思想的に過激化する人や、経済的に困窮して不法行為に手を染める人もいます。こうしたリスクを早期に把握し対処するためには、継続的な確認が必要だと考えられるのです。また、不法滞在を抑止する効果も期待されます。入国後も常に確認が行われていると知れば、滞在期限を守る意識が高まります。制度の信頼性を維持するうえで、継続的なチェックは大きな意味を持ちます。
このように、継続審査は国民に安心を与え、社会全体の安全を確保する仕組みとして肯定的に受け止められる面があります。治安を守る責任を担う政府にとっては、導入する大きな意義があるといえるでしょう。
外国人に広がる安心と不安の二面性
しかし、安全確保としてのメリットがある一方で、この制度は外国人に複雑な影響を与えます。外国人から見れば、継続審査は「守られている」という安心と、「常に疑われている」という不安の両方をもたらします。制度は安全のためと説明されても、監視されている感覚は消えません。外国人自身が「信用されていない存在」と受け止めれば、心理的な負担は大きくなります。
さらに、周囲の社会からも「監視対象の人」と見なされる可能性があります。外国人が日常的に警察や行政から確認を受けやすくなると、地域住民の目線も変わります。「あの人たちは常にチェックされている」と意識されれば、社会的な距離感が広がるのです。本人の行動や努力とは関係なく、外国人であること自体が「不安要素」として扱われてしまう。これが安心と不安の二面性を際立たせる要因です。
また、SNSなどのオンライン活動まで審査の対象となると、自由な表現が制限されるように感じる外国人も増えます。誤解を恐れて発言を控える自己規制が広がれば、言論の自由や自己表現の幅は狭まります。これは単なる制度上の問題ではなく、外国人の日常生活の質や社会参加の意欲に直結する深刻な課題なのです。
特に問題なのは、この「自己規制」が習慣化してしまう点です。本来は自由に意見を言えるはずの場でも、外国人が自ら発言を控え続ければ、周囲から「黙っている人」「従順な人」と誤解されることもあります。その結果、外国人は声を失い、社会的な立場が弱まる悪循環に陥ります。制度の存在そのものが、外国人を萎縮させてしまうのです。
日常生活に忍び込む新しい分断と偏見
継続審査の仕組みが外国人の生活に具体的にどのような影響を与えるのかを考えると、そこには新しい分断と偏見の芽が見えてきます。まず雇用の場面では、外国人を採用する企業が「ビザが取り消される可能性がある人材はリスクが高い」と判断し、採用を避けるケースが増えるかもしれません。これは制度上の安全策として合理的に思えても、外国人からすれば不当な差別です。能力や実績よりも「制度上のリスク」というレッテルが重視されてしまうのです。
住居の場面でも同じことが起こり得ます。大家や不動産業者が「監視されている外国人はトラブルを招きやすい」と考え、契約を断るケースです。すでに日本でも外国人が部屋を借りにくいという現実がありますが、制度が強化されればこの傾向はさらに悪化するでしょう。
教育の現場でも影響は避けられません。子どもが「監視対象の家庭の子」と見なされれば、いじめや孤立の原因になります。家庭に問題がなくても「外国人だから」という理由で偏見を受ける。これが制度の副作用として現れるのです。
さらに、制度の運用に「国籍フィルター」が働く可能性もあります。表向きはすべての外国人に平等に適用されるとされても、実務では特定の国や地域の出身者に重点的なチェックが行われやすいのです。これにより、特定国出身というだけで疑われやすくなり、社会的な偏見が固定化されます。継続審査が差別を正当化する土壌になってしまう危険があるのです。
また、地域社会への影響も見逃せません。外国人が「監視対象」と見なされることで、地域の交流や信頼関係が築きにくくなるのです。自治会や学校行事への参加を控える外国人が増えれば、地域とのつながりは弱まり、孤立が進みます。結果として「外国人は地域に溶け込まない」との印象が広がり、さらに偏見が強化されるという悪循環を生むのです。制度がもたらす分断は、外国人と社会の双方に不利益を与えかねません。
共生社会を実現するために求められる視点
では、こうした課題にどう向き合えばよいのでしょうか。第一に必要なのは制度の透明性です。どのような行為が違反とされ、どのような基準で判断されるのかを明確に示すことが重要です。不透明な制度は外国人の不安を増幅させ、社会の偏見を強めます。
第二に、公平性の実効性を確保することです。国籍や出身国によって扱いが変わるのではなく、行動や生活実態に基づいて判断する仕組みが必要です。制度が「特定の国の人には厳しい」という印象を与えれば、差別を助長するだけです。
第三に、外国人自身の声を制度設計や運用に反映させる仕組みを整えることです。当事者の視点を取り入れることで、不公平感を減らし、制度に対する信頼を高めることができます。外国人を「一方的に見張られる存在」ではなく「社会の一員」として尊重する姿勢が不可欠です。
最後に、受け入れる社会全体の意識が問われます。外国人を「リスク要因」として排除するのではなく、共に暮らす仲間として理解する姿勢が必要です。制度を安全のために導入しても、その存在が差別や偏見を正当化する理由になっては本末転倒です。教育や情報発信を通じて、共生を支える意識を社会に広げていくことが求められます。
継続審査は治安維持のための合理的な手段である一方で、共生社会を遠ざける危険を秘めています。外国人が安心して暮らすためには、制度の透明性、公平性、そして社会の理解が不可欠です。安全と共生をどう両立させるか。その問いに向き合うことこそが、これからの日本社会に課せられた課題なのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。