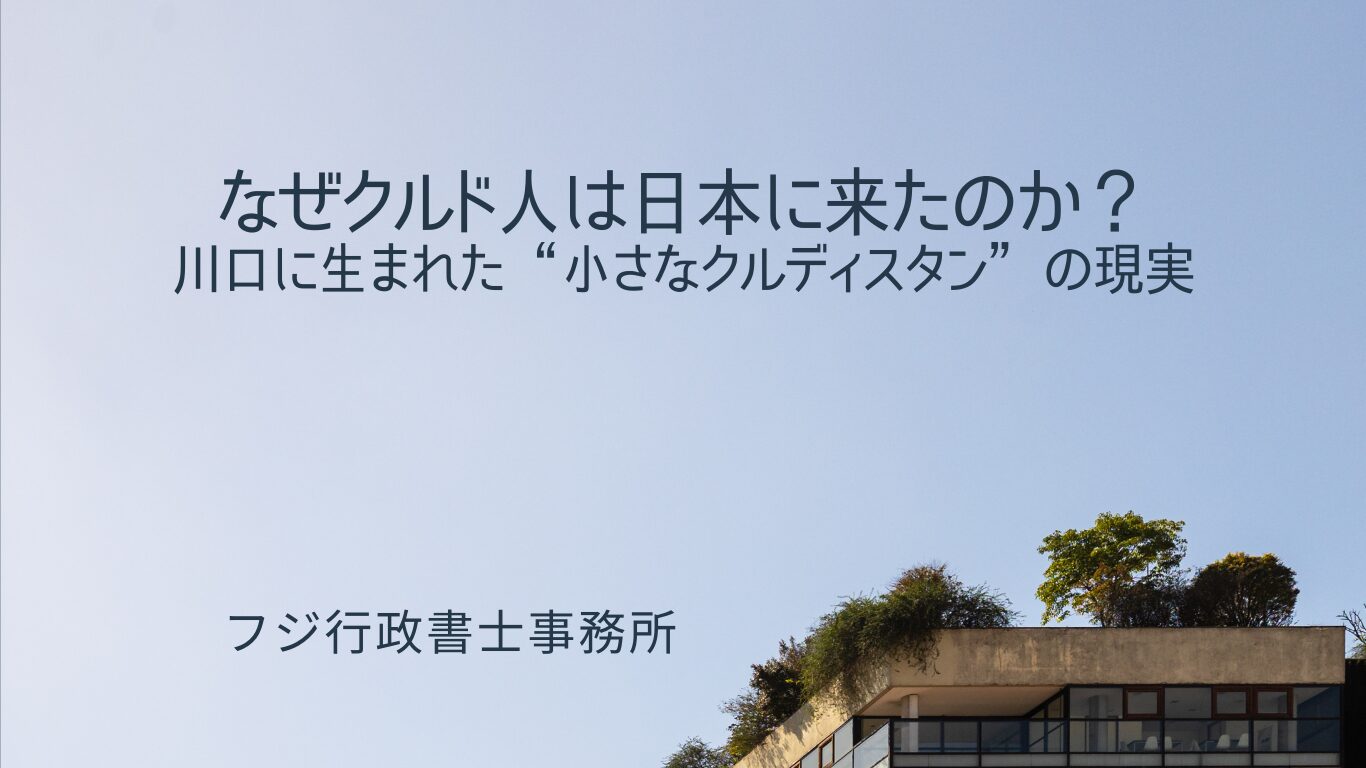なぜクルド人は日本に来たのか――迫害と亡命の現実
クルド人は、世界で最も大きな「国を持たない民族」として知られています。人口は3,000万から4,000万人にのぼり、主にトルコ、イラク、イラン、シリアにまたがる山岳地帯に暮らしています。彼らは自らを独自の言語と文化を持つ民族と認識し、国家を持たずとも誇りを失わずに生き続けてきました。しかし、近代以降の国境再編により分断され、少数派として生きざるを得なくなった歴史があります。
とくにトルコに暮らすクルド人は、長年にわたって厳しい同化政策の対象とされてきました。公的な場でのクルド語使用は制限され、文化活動も抑圧されることが多々ありました。1980年代以降には、クルド労働者党(PKK)による独立運動が武装闘争に発展し、トルコ政府は徹底的な弾圧を開始しました。その結果、PKKと無関係な一般のクルド人まで「潜在的な危険分子」とみなされ、監視や拘束の対象となったのです。
こうした状況から、多くのクルド人が国外への逃亡を余儀なくされました。ヨーロッパに渡る人々もいれば、意外なことに遠い日本を目指した人々もいました。日本を選んだ理由はさまざまですが、当時の入国管理制度の隙間を利用できたこと、政治的迫害から逃れて安全な国で暮らしたいという思いが大きな動機でした。1990年代から2000年代初頭にかけて、トルコ出身のクルド人が続々と来日し、難民申請を行いました。
しかし、日本の難民認定率は極めて低く、ほとんどの申請は却下されました。認められなかった人々は「仮放免」という不安定な立場で暮らすことになります。仮放免とは、本来なら国外退去を命じられる立場でありながら、人道的な理由から一時的に日本での生活を許される制度です。就労は禁止、健康保険への加入も認められず、移動にも制限がかかるという厳しい条件が課せられます。にもかかわらず、彼らは祖国に戻れば迫害が待っているため、日本にとどまるしかなかったのです。
川口に集まったクルド人――“小さなクルディスタン”の誕生
クルド人が日本で生活基盤を築く上で重要な役割を果たしたのが、埼玉県川口市にある芝園団地です。ここは高度経済成長期に建設された大規模住宅で、日本人住民が減少した後に外国人が多く入居するようになりました。自然とクルド人同士が集まり、互いに支え合える環境が生まれていったのです。
言葉も文化も異なる日本で、孤立せずに暮らしていくためには仲間の存在が不可欠でした。同じトルコ出身で同じクルド語を話す人々が近くに暮らすことで、仕事探しや生活情報の共有、子どもの教育に関する相談などを支え合うことができました。結婚式や宗教行事を共同で行える環境は、民族としての誇りを維持するうえでも重要でした。こうして芝園団地周辺には「小さなクルディスタン」と呼べるようなコミュニティが形成されていきました。
コミュニティの存在は、安心感を与えると同時に、日本社会から見れば「異質な集団」として映ることもあります。独自の生活リズムや文化的習慣が可視化されることで、地域住民との間に距離感が生じることも少なくありません。例えば、食文化や生活音、宗教行事に伴う人の出入りなどが摩擦のきっかけになることがあります。しかし、彼らにとっては自らのアイデンティティを守るための自然な営みでした。
このように、クルド人のコミュニティは困難な状況にあっても「互いを支え合う」という強い結束の中で育まれてきたのです。その一方で、コミュニティの存在そのものが地域社会との間に緊張関係を生む要因ともなっています。
日本での暮らしと葛藤――仮放免・学校・働けない現実
クルド人が日本で直面する最大の問題は、在留資格の不安定さです。難民認定がほとんど認められない日本では、仮放免状態が長期化し、生活に深刻な制約がかかります。就労は原則禁止のため、生活費を得る手段は限られ、非正規の仕事に頼らざるを得ない状況が続きます。これが摘発のリスクを高め、家族の暮らしをさらに不安定にしているのです。
健康保険に加入できないことも大きな問題です。病気やけがをしても高額な医療費がかかり、十分な治療を受けられないことがあります。特に子どもがいる家庭では、教育と医療の両面で不安がつきまといます。子どもたちは日本の学校に通い、日本語を学び、日本人の友人と遊ぶことで社会に溶け込んでいきます。しかし、親が安定した在留資格を持たないために、将来の生活設計が立てられません。進学や就職の段階で立ちはだかる壁は大きく、子どもたちの夢を制限する現実があります。
学校現場でも、クルド人の子どもをどう支援するかが課題となっています。日本語教育のサポートや文化の違いへの理解が求められていますが、十分な体制が整っているとは言えません。先生や同級生との間に誤解が生じることもあり、子どもたちが孤立感を覚えることもあります。それでも子どもたちは懸命に学び、地域社会に馴染もうと努力しています。
このような暮らしの中で、クルド人は常に「ここに居場所があるのか」という不安と向き合わなければなりません。安定を求めて日本にやってきたにもかかわらず、制度の壁が彼らを不安定な立場に置き続けているのです。
地域社会での摩擦と対話――警察トラブルから見える課題
日本社会の中で暮らすクルド人は、ときに地域との摩擦に直面します。2023年には、川口市でクルド人男性と警察官との間に職務質問をめぐるトラブルが発生し、全国的なニュースとなりました。この出来事はSNSでも大きな議論を呼び、「クルド人が問題を起こしている」という批判と「制度や偏見が問題だ」という擁護が対立しました。個人の行動だけでなく、制度のあり方そのものが問われたのです。
また、地域住民との間でも生活習慣の違いから誤解が生じることがあります。ゴミ出しのルールや騒音、祭りやイベントでのふるまいなど、日本人住民から見れば「違和感」となる点が摩擦の原因になることがあります。一方で、クルド人側からすれば、母国では当たり前の行為であり、文化的背景を知らずに誤解が生まれるケースが多いのです。
しかし、摩擦だけがすべてではありません。地域にはクルド人を支援しようと活動する団体や、積極的に交流を図る日本人住民もいます。学校行事や地域イベントで子どもたちが活躍する姿が、日本人とクルド人をつなぐ架け橋になることもあります。小さな成功体験の積み重ねが、互いの理解を深めるきっかけとなるのです。
クルド人の存在は、日本社会が多様性をどう受け止めるかを試す鏡のようなものです。摩擦は避けられないかもしれませんが、その一方で対話や理解の可能性も常に存在しています。行政書士をはじめとした専門家が在留資格の安定を支えることは、地域社会全体の安心につながります。そして、彼らを「遠い国の民族」としてではなく、同じ街で生きる隣人として受け止める姿勢が問われているのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。