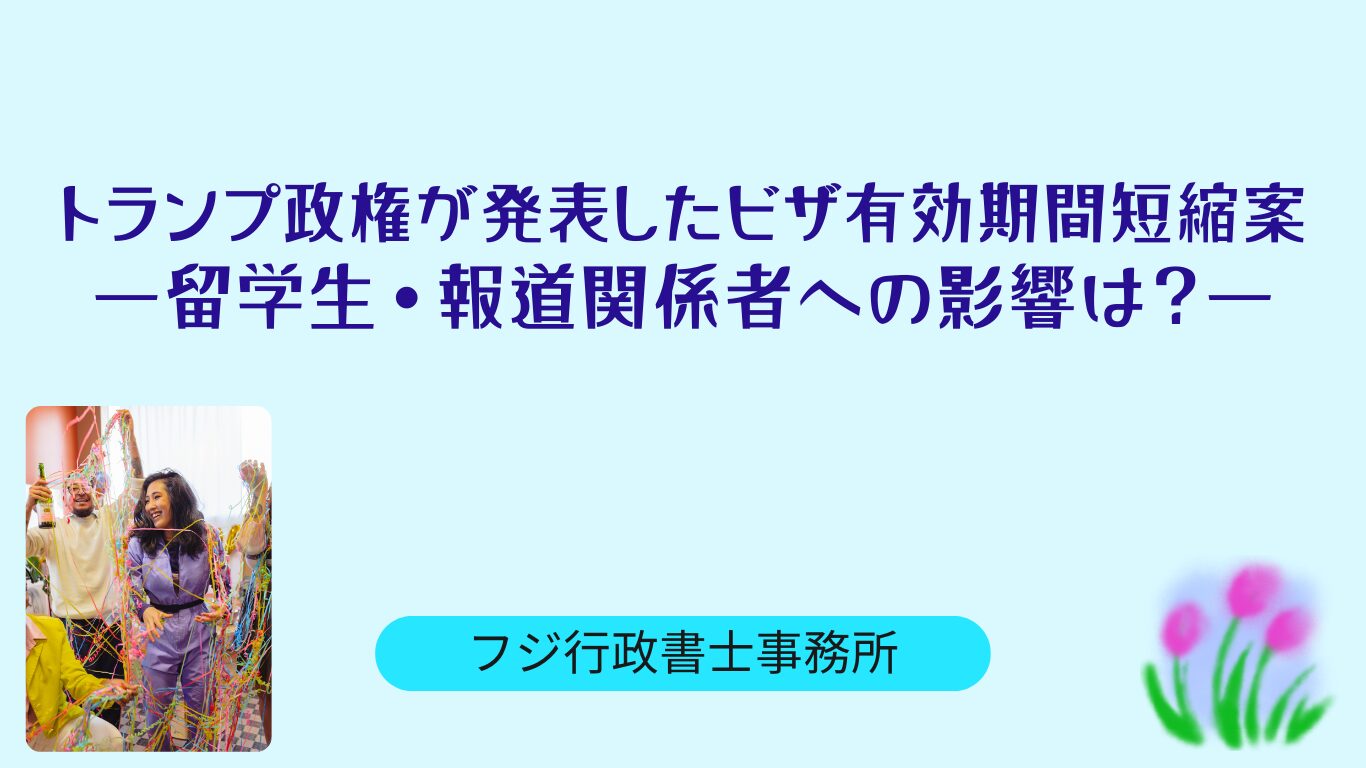トランプ政権が打ち出したビザ有効期間短縮案の波紋
2025年8月27日、トランプ政権は国土安全保障省を通じて、外国人留学生(Fビザ)、文化交流プログラム参加者(Jビザ)、報道関係者(Iビザ)のビザ有効期間を短縮する新しい規制案を公表しました。すでにパブリックコメントの募集も始まっており、制度が現実のものとなれば、日本を含む各国からの渡航者にも大きな影響が及ぶと見込まれています。
これまで留学生や文化交流プログラムの参加者には「D/S(Duration of Status)」と呼ばれる制度があり、学校に在籍している限りは在留資格が維持される仕組みが一般的でした。しかし、今回の規制案ではその制度を廃止し、FビザとJビザを最長4年に制限することが明記されました。学業やプログラムがそれ以上に及ぶ場合には、延長のために改めて移民局へ申請を行わなければならなくなります。
さらに、報道関係者向けのIビザについても大きな制限が課されることになります。これまでは比較的長期にわたり滞在が認められてきましたが、規制案では最長240日とされました。加えて、中国籍の報道関係者については90日という極端に短い期限が設定されており、安全保障上の懸念が背景にあるとみられています。
政権側は「ビザを悪用して恒常的に居住しようとするリスクを軽減し、監督体制を強化するため」と説明しており、外国人の在留管理を一層厳格化する姿勢を鮮明にしています。こうした新しい制度設計は、今後のアメリカ社会における外国人の立場を大きく変えかねず、制度改革以上の意味を持つことは間違いありません。
どうしてここまで厳しくするのか
今回の規制案が「なぜここまで制限的なのか」という点については、いくつかの理由が考えられます。
第一に、不法滞在への強い警戒があります。アメリカでは不法移民の数が数百万人規模にのぼっており、その中にはビザの期限を過ぎても帰国しない人々が少なからず含まれています。特に留学生ビザや交流ビザは在籍している限り滞在可能という柔軟な制度であったため、「学業やプログラムを口実に実際は居座る」という懸念が指摘されてきました。そのため、数年ごとに審査を受けさせることで、常に身元確認ができる体制を整えたいという思惑があるのです。
第二に、国家安全保障上の観点です。近年アメリカは、スパイ活動や情報漏洩のリスクに敏感になっています。特に報道ビザは、報道の自由を理由に比較的長期の滞在が可能でしたが、一部の国の報道機関が実際には諜報活動を行っているのではないかという疑念を持たれています。今回の中国人記者に対する90日の制限は、まさに安全保障上の警戒心を形にしたものといえます。
第三に、国内政治的な要素です。トランプ政権は移民や外国人に厳しい姿勢を打ち出すことで支持層からの支持を固めてきました。外国人に対して制限を強化することで「アメリカ人の雇用と安全を守る」というメッセージを有権者に送る狙いがあります。つまり、今回の規制は実務的な側面だけでなく、政治的なパフォーマンスという意味も持っているのです。
第四に、過去の経緯も影響しています。2020年にも同様の案が提示されましたが、教育機関や業界団体からの反発を受け、2021年にはバイデン政権が撤回しました。今回の再提出は、過去に実現できなかった改革を再び実現しようとする「リベンジ」の意味合いも強いといえます。こうした背景を考え合わせれば、今回の厳格化は単なる制度変更ではなく、アメリカ国内の不安や対立を映し出した象徴的な動きだと理解できます。
アメリカ離れは進むのか
このような規制が現実化すれば、当然ながら「アメリカ離れ」が進むと予想されます。
まず留学生の心理的な不安が大きいです。これまでは卒業まで安心して学業に専念できましたが、最長4年という期限が設けられると、途中で延長申請が認められない可能性を常に意識せざるを得なくなります。大学院や研究職を目指す場合には計画が立てづらくなり、結果として「他国への留学を選ぼう」という流れが加速するでしょう。
実際、アメリカの留学人気はすでにカナダ、イギリス、オーストラリアなどに押されつつあります。これらの国々はビザ延長や永住権への道筋が比較的明確で、留学生を積極的に受け入れる姿勢を示しています。アメリカが規制を強めれば、さらに人材が他国へ流出するのは避けられません。
また、大学や研究機関にとっても深刻な問題です。世界中から優秀な人材を集めてきたことがアメリカの学術的優位を支えてきましたが、留学生が減少すれば国際的な評価や競争力が低下しかねません。さらに企業にとっても、特にハイテク産業では留学生や研究者がそのまま就職し、イノベーションを支えてきた歴史があります。外国人の流入が減ることは、長期的には技術力の低下につながるリスクがあるのです。
加えて、国際的なイメージの問題もあります。アメリカが「外国人に厳しい国」という印象を持たれれば、短期の語学研修や文化交流ですら敬遠されるかもしれません。その結果、留学だけでなく観光や交流全般が縮小し、ソフトパワーの低下という副作用も生じるでしょう。結局のところ、管理強化で自国を守る姿勢は理解できるものの、世界中の人材や信頼を失うという代償を払うことになるのです。
日本とアメリカにおける外国人労働者の必要性の違い
最後に、そもそも「アメリカは日本ほど外国人労働者を必要としていないのか」という疑問について触れてみます。
日本は少子高齢化によって急速に人口が減少しており、社会全体で人手不足が顕在化しています。介護、建設、農業、サービス業など幅広い分野で人材が不足しており、外国人労働者なしでは成り立たない状況にあります。まさに外国人がいなければ社会や産業が維持できないほど必要性が高いのです。
一方、アメリカも出生率は低下しているものの、日本のように急激な人口減少ではありません。労働力不足が特に強く表れているのはITエンジニアや研究者、医療従事者などの高度人材分野です。また農業やサービス業では中南米からの移民労働者に依存しており、実際には外国人なしでは成り立たない部分も多いのですが、日本のように国全体で労働力不足に直面しているわけではありません。
さらにアメリカは移民国家であり、すでに人口の14%前後が移民です。日本の約2%と比べれば圧倒的に多く、これ以上の受け入れには政治的な抵抗感が強いのが実情です。外国人をさらに増やすのではなく、今いる移民をどう管理するかという議論の比重が高くなっているのです。
したがって、アメリカは外国人労働者を「必要としていない」のではなく、すでに受け入れている規模が大きいため、追加の受け入れに慎重になっているというのが実態です。日本は人口減少による労働力不足で外国人を不可欠とせざるを得ないのに対し、アメリカは分野ごとの必要性は大きいものの「もう十分」という空気が強いのです。こうした違いを踏まえると、両国にとっての外国人政策はそれぞれの社会背景を反映したものとなっていることが分かります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。