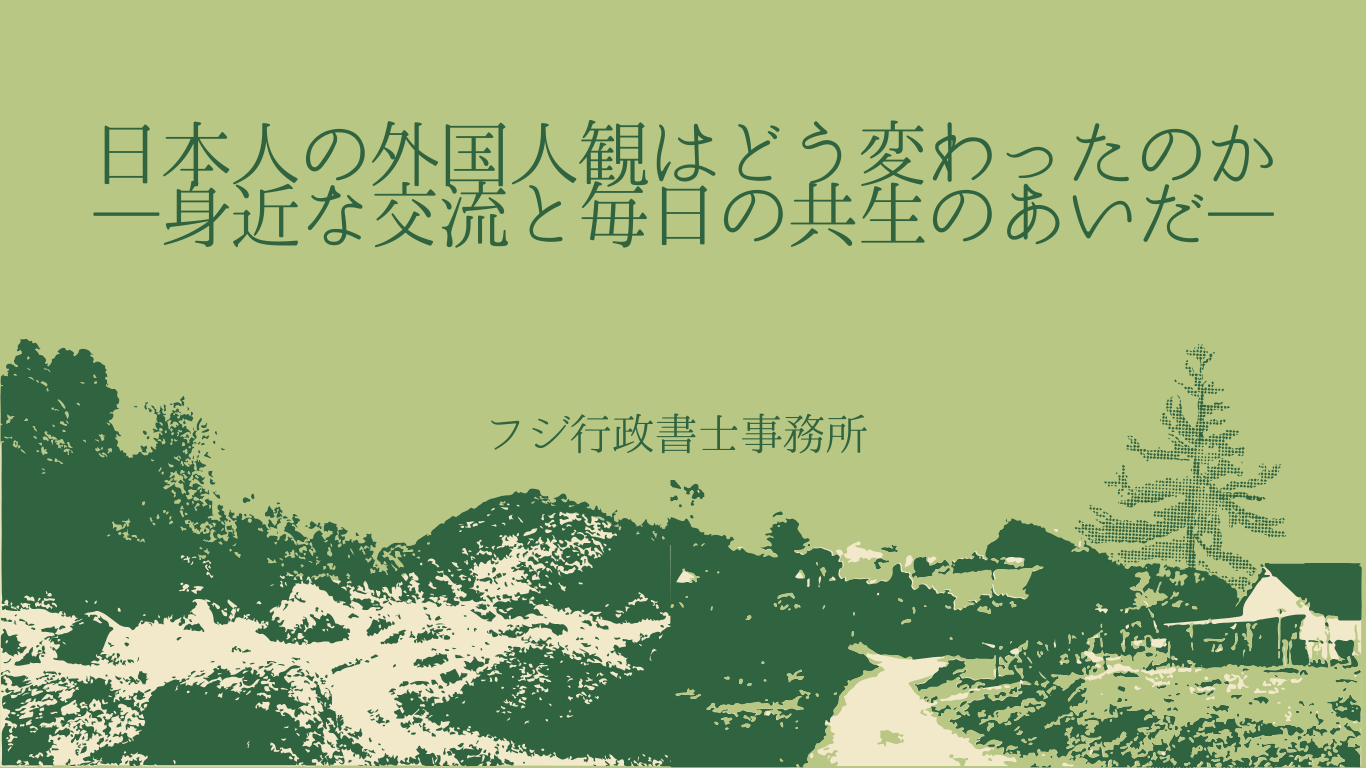日本人の外国人観はどのように変化してきたのか
ここ数十年の間に、日本人の外国人に対する意識は確実に変化してきました。かつては「外国人=一時的に滞在する旅行者」というイメージが強く、日常生活の中で外国人と接する機会は限られていました。しかし、1990年代に入管法が改正され、日系人労働者が大規模に受け入れられたことや、技能実習制度の拡大、そして近年の特定技能制度の創設などにより、外国人が日本社会に定着する流れが強まりました。これに伴い、日本人が外国人を「同じ地域で共に暮らす住民」として意識せざるを得ない状況が生まれています。
統計的にも、外国人労働者は増加の一途をたどり、2025年には200万人を超える規模となりました。街を歩けば、コンビニ、飲食店、介護施設など、身近な場面で外国人と接する機会が増えています。日本人の意識調査を見ても、「外国人労働者を受け入れることに賛成」とする回答は7割を超える調査が多く、かつてのような排他的な傾向は和らぎつつあることがうかがえます。
ただし、この変化は一様ではありません。若い世代ほど多文化共生に前向きであり、SNSや留学、国際交流を通じて外国人との接触経験が自然なものとなっている一方で、中高年層は「生活が近づきすぎること」への不安を口にするケースが少なくありません。つまり、日本人の意識は全体としては開かれつつも、世代や立場によって受け止め方に大きな差が存在しているのです。
ふれあいは歓迎されるが、日常的な共生には抵抗が残る
調査結果を詳しく見ると、日本人の外国人への意識には「距離感による段階差」がはっきりと見えてきます。例えば、地域のイベントや祭り、スーパーでの買い物、飲食店での接客といった短時間の交流に関しては、多くの日本人が「自然に受け入れられる」と回答しています。こうした場面は一時的な接触であり、異文化に触れる楽しさや新鮮さを感じる機会として肯定的に受け止められやすいのです。
一方で、職場で毎日一緒に働くことや、家庭内の介護・教育といった生活の根幹に関わる場面では、抵抗感が強まる傾向があります。パーソル総合研究所の調査でも、外国人が店員や同僚として関わることには比較的寛容である一方、「自分や家族の介護を外国人に任せること」に対しては慎重な姿勢が見られました。つまり、表面的な交流は歓迎されても、日常生活の深い部分に外国人が関わることには心理的な壁があるということです。
この背景には、言語の壁や文化の違いに対する不安があります。特に職場では細かな意思疎通が必要であり、価値観の違いが衝突につながるのではないかという懸念が根強く存在します。加えて、介護や医療、教育など責任が伴う領域では、信頼や安心感を得にくいと感じる人が多いのです。外国人を「よそから来た人」ではなく「同じ社会の一員」として受け入れるためには、この“深い関わり”における心理的な抵抗を和らげる工夫が求められます。
世代差と経験が意識を左右する
日本人の外国人観には、世代による明確な差が存在しています。若年層は、SNSや海外旅行、留学経験を通じて外国人や多文化に触れる機会が多く、自然に外国人を受け入れる傾向が強いといえます。例えば、大学や専門学校で留学生と一緒に学ぶことは今や珍しくなく、アルバイト先で外国人同僚と働くことも当たり前になっています。こうした経験を通じて育った世代は、職場や地域で外国人と共生することに抵抗が少ないのです。
一方、中高年層は「ふれあいなら歓迎するが、毎日は少し負担」と感じやすい傾向があります。これは、自身が若い頃に外国人と接する機会がほとんどなかったことや、言語・文化の違いを乗り越える経験が少なかったことが影響しています。また、仕事や家庭で責任を背負う立場にあるため、「もし意思疎通で問題が起きたらどうするのか」といったリスク意識が強く働くことも一因です。
さらに、外国人と接する経験の有無も意識を左右します。交流経験がある人ほど肯定的な意識を持つ傾向が明らかになっており、接触機会が心理的ハードルを下げる役割を果たしているのです。つまり、「知らないから不安」「経験していないから抵抗がある」という構造が根底にあり、接触経験の有無が世代差をさらに拡大させています。
共生社会に向けた課題とこれからの可能性
日本人の外国人観は、確かに変化してきています。旅行者や一時滞在者としてではなく、労働者、地域住民、子どもたちの親といった多様な立場で外国人が社会に定着するようになったことで、共生の必要性が高まっているのです。しかしその一方で、「短時間のふれあいは良いが、日常的に深く関わることには抵抗がある」という二重構造は依然として強く残っています。
この壁を越えるためには、地域や職場における小さな接触の積み重ねが重要です。自治体やNPOによる日本語教室や地域交流イベントは、外国人と日本人が自然に出会い、理解を深めるきっかけになります。また、企業においても、外国人社員と日本人社員が協働しやすい環境を整えるための研修やサポート体制が求められます。単なる労働力として外国人を受け入れるのではなく、生活者・住民として共に生きるという視点が不可欠です。
さらに、教育の場も大きな役割を果たします。子どもたちが学校で外国人の同級生と学び遊ぶことで、将来的に多文化共生を自然に受け入れられる世代が育ちます。つまり、世代が変わるにつれて「外国人と毎日一緒に過ごすこと」が当たり前の社会へと移行していく可能性があるのです。
結局のところ、日本人の外国人観は「変わりつつあるが、まだ途上にある」といえます。現状では短期的な交流が中心であり、日常的な共生には壁が残っていますが、接触機会の増加や世代交代によって、この壁は徐々に低くなっていくでしょう。共に生きる社会を実現するためには、意識の変化を待つだけでなく、制度的・地域的なサポートを積極的に整備していくことが必要です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。