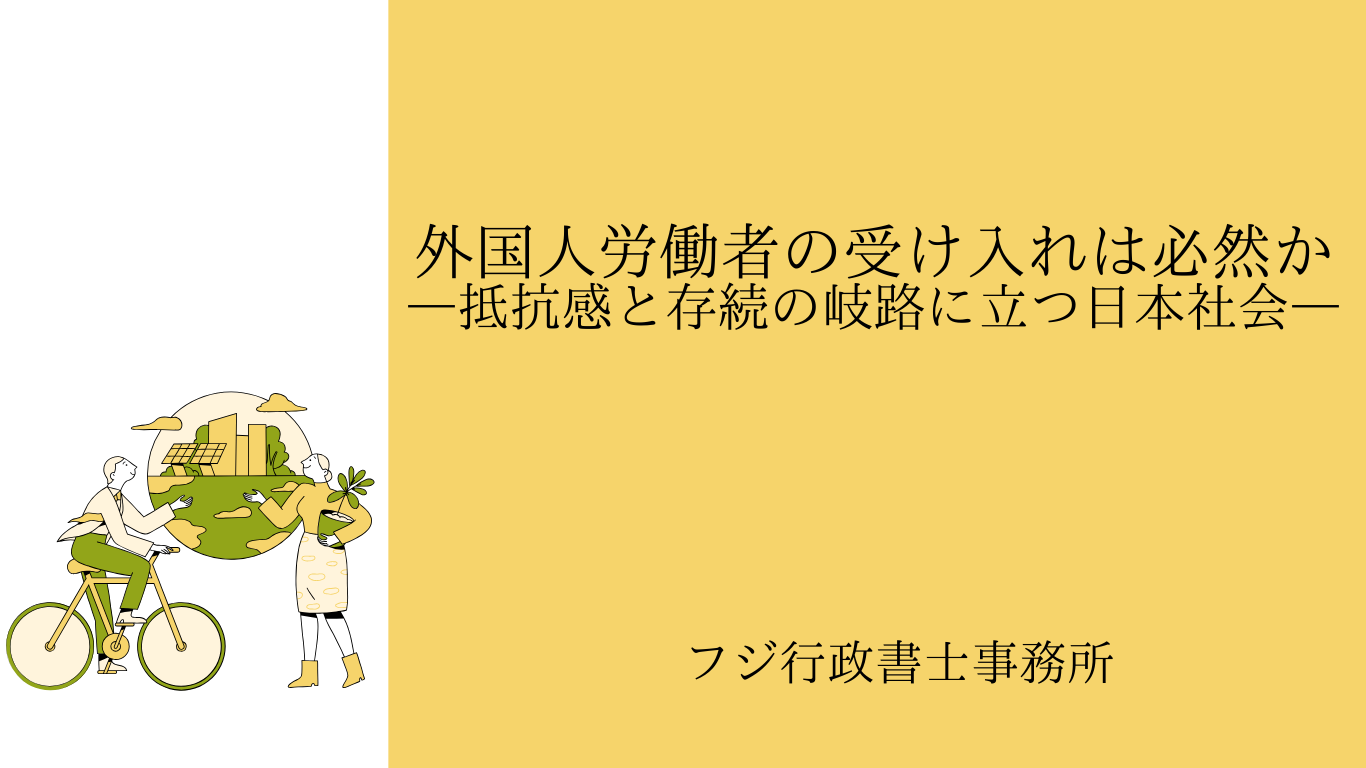人手不足が招く構造的な危機
日本社会は少子高齢化の進行とともに、労働人口の急速な減少に直面しています。特に地方や中小企業においては、従業員の高齢化や若者の流出が重なり、人材の確保はかつてないほど困難になっています。これまで「求人を出せば誰かが来てくれる」と考えていた時代はすでに終わり、採用活動を続けても応募がゼロという企業も珍しくありません。
この背景には、日本全体の人口動態が関係しています。総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1990年代をピークに減少し続けており、今後も加速度的に縮小していくと予測されています。単に一時的な景気の波ではなく、構造的な問題としての「人手不足」が現れているのです。
そうした中で、外国人労働者の受け入れが注目されるようになっています。ある全国調査によれば、回答した企業のうち約78%が「外国人労働者はいない」と回答しています。つまり、多くの企業はまだ積極的に外国人を雇用していないのが現状です。しかし一方で、すでに外国人を受け入れている企業の半数以上が「3年前より増加している」と答え、特に製造業や建設業、農林漁業といった人手不足産業で雇用が拡大している実態も示されています。
ここで重要なのは、外国人雇用がすでに「限定された業種」では当たり前の選択肢になりつつあるという点です。例えば製造業では全従業員の1割以上が外国人という企業も存在し、建設業や農業でも同様に高い比率を示しています。反対に金融業や不動産業、小売業などでは外国人がほとんど働いていないという結果が出ています。つまり、外国人労働者が「社会全体に均等に浸透している」わけではなく、産業によって依存度が大きく異なっているのです。
さらに、統計に現れない領域として、短時間労働の存在があります。コンビニエンスストアや外食産業、清掃業務などでは、留学生や家族滞在者を中心としたアルバイトの外国人がすでに欠かせない存在になっています。しかし今回の調査は「正社員+フルタイム直接雇用」に限定されているため、実際の生活空間で私たちが感じている「外国人が多い」という印象と、調査上の数字との間に乖離が生まれているのです。
「外国人はいない」と回答する企業が大多数を占める一方で、現場では外国人抜きには成り立たない業種がある。この二重構造こそが、いまの日本社会が抱える矛盾を象徴していると言えるでしょう。
抵抗感が根強く残る現実
外国人労働者の受け入れに対して、多くの企業や社会にはまだ抵抗感があります。言語の壁や文化の違いに対する不安、労務管理や在留資格の手続きに伴う負担、さらには既存従業員との軋轢への懸念など、心理的・制度的な障壁は少なくありません。
調査の中でも「3年後の外国人労働者の割合はどうなるか」という設問に対しては、約77%の企業が「変わらない」と回答し、積極的に「増やす」と答えたのは全体の2割程度にとどまりました。つまり、多くの企業は「今後も外国人雇用を広げるつもりはない」と考えているのです。この背景には、単純に必要性を感じていない企業もあれば、必要性を感じつつも受け入れに踏み切れない企業もあります。
特に中小企業では、外国人を受け入れた場合の指導コストやトラブル対応に対する不安が大きく、現状維持を選びがちです。外国人を雇用した経験のない企業ほど、「本当に指示が通じるのか」「日本の商習慣や接客マナーを理解してもらえるのか」といった懸念を強く抱きます。また、不動産業や金融業、小売業など、接客や資格が求められる産業では外国人雇用の割合が極端に低く、依然として「難しい」という認識が強く残っています。
さらに、日本人の働き方や価値観そのものが「同質性」を重視してきた歴史も、抵抗感の根底にあります。戦後の高度経済成長期を通じて形成された「長期雇用・年功序列」を基盤とした労働慣行は、多様な人材の流入を想定していませんでした。結果として「外から来た人を受け入れること」に心理的なハードルが生まれています。
社会全体としても「外国人が急に増えると治安が悪化するのではないか」「地域社会に馴染めないのではないか」といった漠然とした懸念が根強く存在します。現場で日常的に外国人と接している人はその必要性を理解しやすいのに対し、接点の少ない人ほど警戒感を抱きやすい傾向もあります。
つまり、外国人労働者の存在は目に見えて増えているにもかかわらず、多くの人々は「受け入れざるを得ないが、本心では歓迎していない」という矛盾した心理を抱えているのです。
存続か否かという選択
とはいえ、こうした抵抗感を超えて「選択を迫られる」局面がすぐそこまで来ています。調査によれば、もし外国人労働者の受け入れを制限した場合、半数以上の企業が「業績にマイナス」と回答しました。特に中小企業ではその割合が高く、外国人雇用をやめれば事業の縮小や廃業につながる可能性が大きいのです。
これは単なる「外国人を雇うかどうか」という選択ではありません。「外国人を受け入れなければ、企業そのものが存続できるかどうか」という生存の問題です。人材が確保できなければ、事業を続けられないのは当然のことです。現に、介護や建設、物流の現場では「人が来ないから受注を減らさざるを得ない」という声が出ています。
大企業は高度人材やグローバル展開対応といった戦略的観点で外国人を雇用する傾向が強い一方、中小企業は「即戦力としての労働力」を求めています。後者にとって外国人労働者は単なる補助ではなく、事業を継続するための必須条件に近づいているのです。
さらに、外国人労働者が担う役割は、単に労働力の穴埋めにとどまりません。農業や漁業の分野では後継者不足を補い、物流の分野では24時間稼働を支え、介護や医療の分野では高齢化社会を支える担い手となっています。こうした現場が滞れば、消費者や地域住民の生活にも直結する影響が及びます。つまり、外国人を拒めば単に「企業が困る」だけではなく、日本社会全体の基盤そのものが揺らぐのです。
ここで重要なのは、「外国人を受け入れるか、拒むか」という二者択一の問題ではなく、受け入れなければ存続できないという現実です。抵抗感を持ち続けることは自由ですが、その結果として企業や産業が消滅していく未来が待っていることを直視せざるを得ません。
共生社会への舵切りが不可避に
以上のように、外国人労働者の受け入れはもはや「好むか好まないか」の問題ではなく、「持続するか消滅するか」の選択に直結しています。その意味で、日本社会は今、大きな岐路に立っていると言えるでしょう。
国は「共生社会の実現」を掲げていますが、現場の実態を踏まえれば、単にスローガンにとどまらず、制度と環境を整備することが急務です。例えば、言語教育や生活支援、地域社会との橋渡し、労働条件の改善など、外国人が安心して働ける環境を作らなければなりません。同時に、日本人従業員が文化や価値観の違いを理解し、共に働くための意識を育てる取り組みも欠かせません。
教育現場や地域コミュニティでも工夫が求められます。学校に通う外国人の子どもが孤立しないための支援や、多文化交流イベントの開催など、地域レベルでの取り組みが外国人定住の成否を左右します。企業だけでなく、行政や地域社会全体が共生の枠組みを築いていくことが必要です。
また、受け入れる側の企業に対しても支援が不可欠です。外国人労働者の労務管理や在留資格に関する相談窓口の整備、トラブル対応のための専門人材の育成など、企業単独では担えない課題を社会全体で補う仕組みが求められています。こうした制度設計が進まなければ、外国人を雇いたいと考えても実行に移せない企業が増えてしまうでしょう。
すでに外国人労働者は、日本社会の基盤を支える重要な存在となりつつあります。農業や介護、物流、建設など、日常生活や社会インフラに直結する分野では、外国人なくして成り立たない状況が広がっています。これを否定することは、日本社会そのものの持続可能性を危うくすることに他なりません。
結局のところ、私たちが直面しているのは「外国人を受け入れるか否か」ではなく、「外国人と共に生きる社会をどのように築いていくか」という問いです。抵抗感を克服するかどうかにかかわらず、現実はすでに私たちを選択の場へと追い込んでいます。
つまり、日本社会に残された道は一つ――共生への舵を切ることです。それは簡単なことではありませんが、存続のために避けられない選択なのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。