外国人も国民健康保険に加入しなければならないのか
日本に暮らす外国人から最も多く寄せられる疑問の一つが「国民健康保険に入らなければならないのか」というものです。母国では民間保険が中心で、強制加入の仕組みが存在しない国も少なくありません。そのため「なぜ日本では保険料を必ず払わなければならないのか」「短期間しか住まないのに加入が義務なのはおかしい」といった戸惑いの声が多く聞かれます。
確かに、日本の制度は世界的に見ても独特です。国民皆保険制度と呼ばれる仕組みは、すべての住民が医療保障の枠組みに組み込まれることを前提としており、外国人であっても住民登録をした瞬間から対象になります。観光や出張など短期の滞在者は除かれますが、留学生や就労者、家族帯同者など中長期の在留資格を持つ人は原則として加入義務があります。
ここで問題になるのは、外国人本人にとって制度の目的や意味が必ずしも伝わっていないことです。例えば「母国では病気になったら自己負担でも十分安い」「健康保険は会社が用意するものだ」といった価値観があると、日本で役所から「必ず加入してください」と言われても納得しにくいのが現実です。結果として、加入手続きを後回しにしたり、保険料の支払いに消極的になったりする傾向が見られます。
一方で行政側からすれば、外国人であっても日本で生活する以上、医療費を公平に負担してもらう必要があります。病気や事故は国籍に関係なく誰にでも起こり得るものであり、そのときに「未加入だから全額負担」という状況を放置すれば、本人にも社会にも大きな負担が生じます。つまり、制度としては「誰も取り残さない」ために外国人にも加入を求めているのです。
ただし、現場の感覚としては「制度の理念」と「外国人の実感」の間に大きな溝があります。この溝をどう埋めていくかが、日本社会が共生を進めるうえでの課題となっています。
免除や対象外となる場面をめぐる誤解
外国人の間でよくある誤解の一つが、「自分は短期だから加入しなくてもいい」という考え方です。確かに在留資格が3か月未満の場合は国民健康保険の対象外とされています。しかし実際には、当初は短期滞在だったとしても、その後の延長や在留資格変更によって長期化するケースが少なくありません。その場合は結局加入が必要となり、初めから対象外だと誤解していると後から大きな負担を背負うことになります。
もう一つの典型的な誤解は「勤務先で社会保険に入っているから、自分の家族は保険に入れなくてもいい」というものです。確かに会社の健康保険に本人が加入している場合、配偶者や子どもを扶養に含めることができるケースがあります。しかしすべての家族が自動的にカバーされるわけではなく、在留資格や滞在期間によっては扶養にできず、個別に国民健康保険に加入しなければならない場合があります。役所で説明されて初めて知り、慌てて手続きを行う外国人も少なくありません。
さらに、国によっては母国の保険に入っているため「日本でもそれを使えるはずだ」と考える人もいます。実際には日本の医療機関が海外の保険証をそのまま受け入れることはほとんどなく、現金で全額を支払ってから後日海外の保険会社に請求するという流れになります。こうした事情を知らずに「保険に入らなくても大丈夫」と思い込むと、予想外の高額な医療費に直面してしまうことになります。
制度は明確なルールで運用されていますが、外国人にとっては細かい違いが非常にわかりにくいのが実情です。しかも自治体によって説明や運用の丁寧さに差があり、「隣の市ではこうだったのに」と混乱を招くこともあります。行政書士として感じるのは、このような誤解や食い違いが相談のきっかけになることが多いという点です。免除や対象外の条件を整理し、本人の状況に合わせて説明することが、実務的にも非常に重要になります。
家族扶養をめぐる混乱と現場の声
外国人が日本で生活する際に特に悩みが多いのが、家族の保険加入に関する問題です。「自分は会社の健康保険に入っているが、妻は国民健康保険に入らなければならないのか」「子どもが生まれたが、役所にどう届け出ればいいのか」といった相談は頻繁に寄せられます。
この背景には、日本の制度が「個々の在留資格」に強く依存していることがあります。例えば、配偶者が「短期滞在」の在留資格で来日している場合は、どれほど長く一緒に生活していても国民健康保険には加入できません。そのため「同じ家族なのに、病院にかかると負担がまったく違う」という不公平感が生じることもあります。
また、扶養と児童手当の関係も分かりにくさの原因です。国民健康保険に加入していても、児童手当を受け取れるかどうかは住民票の有無や在留資格の種類によって左右されます。結果として「保険料は払っているのに、手当は受けられない」という声もあり、外国人家庭の不満や疑問につながっています。
こうした矛盾は、制度の根底にある「日本社会の一員として同じルールで負担と保障を共有する」という理念と、「外国人は一時的に暮らしているにすぎない」という感覚のせめぎ合いから生まれているといえます。つまり、国としては外国人にも制度を適用して安定的な医療体制を維持したいのに対し、外国人からすると「短期間しかいないのになぜ同じように負担する必要があるのか」という疑問が尽きないのです。
行政書士として現場で感じるのは、こうした感情的な溝をどう埋めるかが非常に大きな課題だということです。単に法律やルールを説明するだけでは十分ではなく、相手の国の制度や文化的背景を理解したうえで「日本ではこういう理由で必要なのです」と伝える姿勢が求められます。
手続きの複雑さと制度の今後
国民健康保険の加入や脱退は、市区町村役場で行います。必要な書類は在留カードやパスポートなどですが、外国人にとっては役所での手続き自体が大きな負担となります。日本語での説明が理解できず、書類の不備を何度も指摘されて疲弊するケースは少なくありません。結局のところ「なぜこんなに複雑なのか」という不満が制度への不信感につながります。
さらに、保険料の算定方法もわかりにくい点の一つです。前年の所得を基準に計算されるため、日本に来たばかりで収入がないのに保険料が高額になる場合もあります。逆に「去年の収入は低かったのに、今年の収入が増えても保険料はしばらく据え置き」ということもあり、制度の仕組みを理解しにくいと感じる外国人は多いのです。
社会全体の視点で見れば、人口減少が進む日本にとって外国人も社会保障を支える一員として重要な存在です。厚生労働省も「外国人だから特別扱いするのではなく、住民として同じルールを適用する」ことを基本姿勢としています。これは公平性を確保するためには当然の考え方ですが、現場では「負担感」と「納得感」の間にずれがあるのが実情です。
今後の課題は、こうした制度の硬直性をどう改善していくかです。例えば、短期滞在者と長期滞在者の区別をより柔軟にしたり、母国の保険との連携を進めたりする取り組みは検討に値します。また、扶養や手当の仕組みも一体的に見直すことで、外国人家庭が「自分たちは制度から取り残されている」と感じにくい環境を整える必要があります。
行政書士としてできることは、外国人に正確な情報を伝えるだけでなく、現場での声を制度改善に反映させるために行政にフィードバックしていくことです。国民健康保険をめぐる不満や誤解は、外国人だけでなく日本人にとっても課題となっています。だからこそ、共生社会を築くためには「加入するのは当然」という一方的な押しつけではなく、「なぜ必要なのか」「どのように改善できるのか」を対話しながら進めていく姿勢が求められるのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
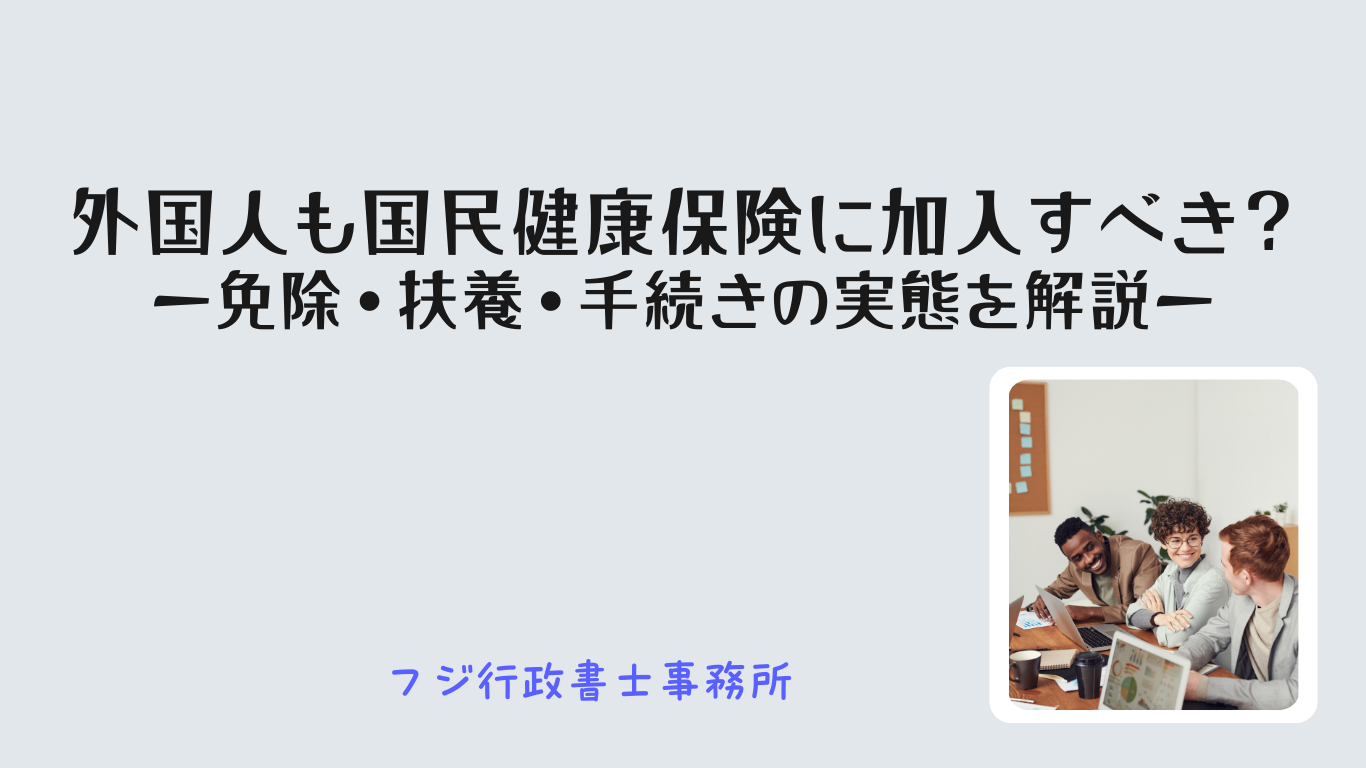

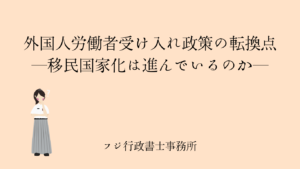
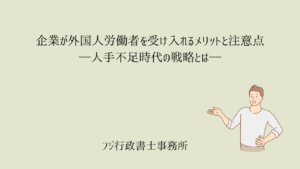
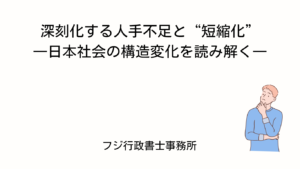
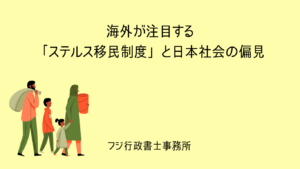

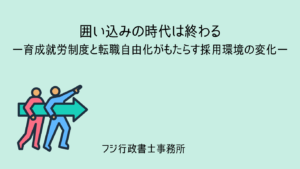
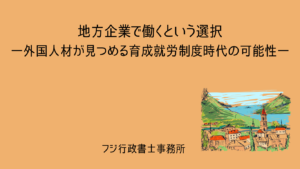
コメント