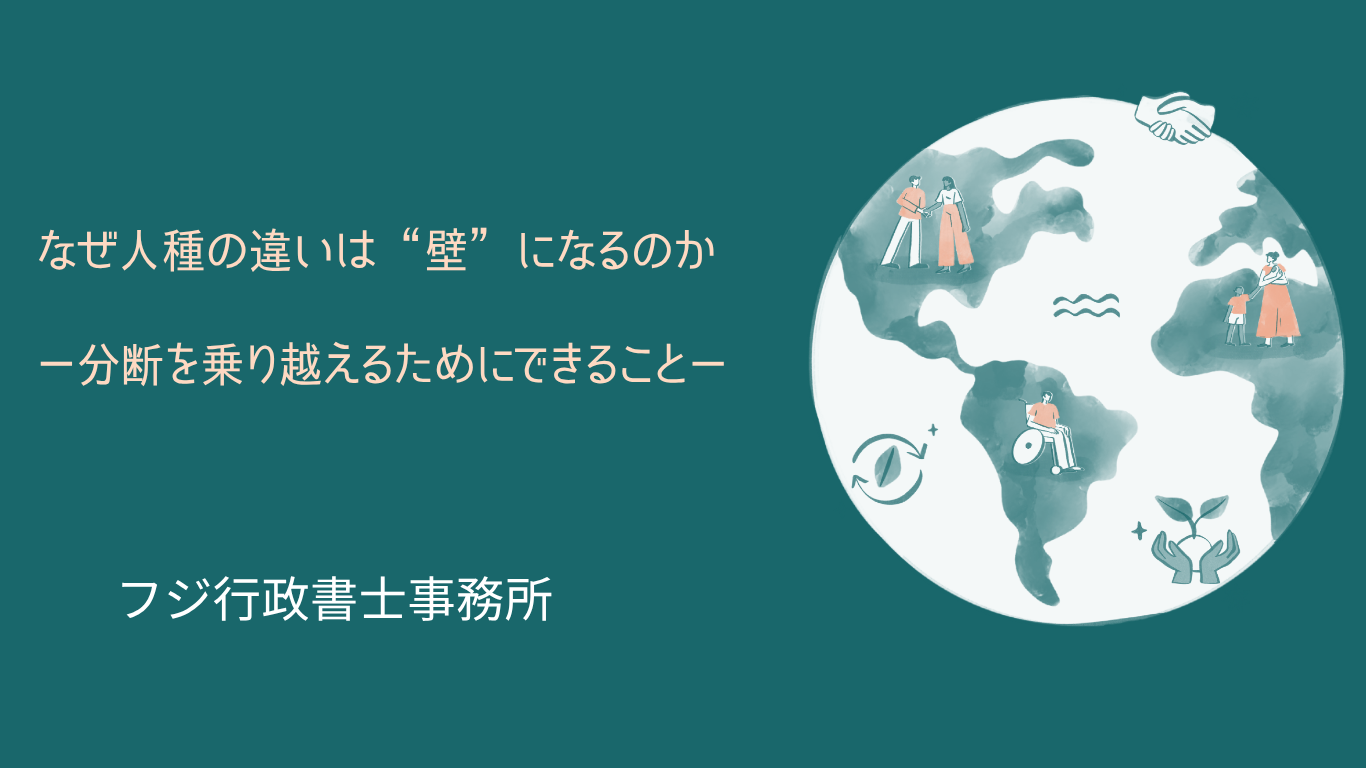差別は誰の心も蝕んでいく
差別がいけないことだというのは、誰もが頭ではわかっていることです。けれど、実際の暮らしの中では、「意識していないつもりの差別」や「構造的に存在する差別」が、日々のように外国人住民の生活を脅かしています。たとえばアパートの入居を断られたり、就職面接で「外国人だから」と理由を告げられずに落とされたりするような事例は、決して特別な話ではありません。
こうした差別がもたらす影響は、単に不利益を被るということにとどまりません。差別の被害にあった人の心には、怒りや不信感、そして自分自身を否定されたような感情が残ります。一方、差別する側にまわった人もまた、「他者を見下すことでしか安心できない心」や、「知らず知らずのうちに誰かを排除してしまう感性」を抱え込むことになります。つまり、加害者も被害者も、どちらもその心を蝕まれていくのです。
問題は、差別が一部の「悪意のある人」によってのみ行われるわけではない、ということです。むしろ、自覚のない差別や、無知によって起きる偏見のほうが、地域社会に深く根を下ろしているのかもしれません。そしてそのような無意識の態度こそが、最も厄介で根深い差別のかたちだと言えるでしょう。
そのため、私たちは「差別はいけない」という表層的な道徳論を唱えるだけではなく、その背後にある社会構造や心理の仕組みに目を向け、具体的にどのように「共に生きる」社会を築いていくかを考える必要があります。
なぜ「人種の違い」は特に難しいのか
文化の違い、宗教の違い、言語の違い。さまざまな違いがある中で、「人種の違い」はとりわけ厄介な壁を生みがちです。その理由のひとつは、外見的な特徴によって、たとえ日本語を流暢に話し、長く日本に暮らしていたとしても、周囲から「日本人ではない」と見なされ続けるという現実があるからです。
つまり、本人の努力や適応の程度とは無関係に、見た目だけで「内か外か」が決められてしまう。この視線が、外国人当事者にとってどれほど強烈な排除感や孤立感を生むかは、想像に難くありません。
また、「外から来た人」に対して漠然とした不安や恐れを抱く心理もあります。これは個人の悪意というより、人間の防衛本能に近いものかもしれません。しかし、その不安が「外国人はマナーが悪い」「怖い」「危険だ」といったステレオタイプに変換されるとき、偏見が生まれます。偏見が繰り返されれば、それはやがて差別という形になります。
地域社会でも、この「見た目による線引き」はしばしば問題を引き起こします。町内会や子ども会、学校の保護者会など、地域の活動において、外国人家庭が「よそ者」として扱われ、参加しにくい空気が生まれることがあります。声をかけられない、情報が回ってこない、何となく距離を置かれる――それが積み重なることで、外国人住民は孤立し、地域から離れていってしまうのです。
さらに、人種による偏見は一度根付くと、次世代にまで引き継がれてしまうことがあります。親が感じた疎外感を、子どもが引き受ける。そして「自分はこの町の一員ではない」と感じながら育つ若者が、また新たな壁を感じてしまう。こうして差別は、静かに、しかし確実に地域社会の分断を深めていくのです。
世界各地に共通する「摩擦」とその背景
人種差別や外国人排斥の問題は、日本だけで起きていることではありません。フランスでは移民系の若者と警察との間で繰り返される衝突があり、アメリカではアジア系住民に対する暴力事件が報道されています。ヨーロッパ諸国でも、移民の流入に対して自国民の不満が高まり、極右政党が台頭するなど、対立の構図は世界中で見られるようになりました。
なぜ、どの国でも移民や外国人との間に摩擦が起きるのでしょうか。その背景には、経済的な不安が大きく関わっています。自国の雇用が不安定になると、「外国人に仕事を奪われているのではないか」という不満が生まれます。また、福祉や医療といった限られたリソースが、「なぜ自分たちよりも外国人に向けられるのか」という疑問を生むこともあります。
さらに、グローバル化によって価値観が多様化し、それに適応しきれない人々が「自分たちの文化や生活様式が脅かされている」と感じることで、排他的な動きが強まる傾向もあります。特に保守的な地域では、「昔ながらの暮らし」を守ろうとする意識が、外国人に対する不信感となって表れることもあるのです。
しかし、こうした対立の多くは、実際には「顔の見える関係」がないことから生まれているケースが少なくありません。つまり、移民や外国人を「個人」ではなく「集団」や「数字」としてしか捉えられていないという問題です。「あの〇〇さん」という具体的な存在ではなく、「外国人全体」という漠然としたイメージで語られてしまうことで、誤解と恐れが増幅されていくのです。
だからこそ、他国の例を見るときにも、単に「差別がある国」として非難するのではなく、「それでも共に生きようとする努力の途中にある社会」として捉えることが必要です。そして、日本もまた、その過渡期のただ中にあるのだと受け止めるべきではないでしょうか。
地域でできる「分断を越える」実践とは
では、具体的に私たちが暮らす地域社会では、どのようにして人種や出自を越えた「共に生きる関係」を築くことができるのでしょうか。正解は一つではありませんが、いくつかの実践例がヒントになります。
ひとつは、生活の場での自然な接触機会を増やすことです。たとえば、地域の清掃活動や祭り、子ども会の行事などに、外国人住民も気軽に参加できる仕組みを作る。多言語での案内や、参加ハードルの低いイベント設計など、ほんの少しの配慮が、心の距離を縮めるきっかけになります。
また、外国人当事者が「語る機会」を持つことも大切です。地域の広報紙でインタビューを掲載したり、外国出身の住民が自国の文化や食を紹介する場を設けたりすることで、名前と顔を持った関係性が育まれます。「あの人の話を聞いて、印象が変わった」という声は、思いのほか多く聞かれます。
さらに、制度的な後押しも欠かせません。市区町村レベルで多文化共生を進める条例を制定したり、外国人住民を対象とした相談窓口を整備することは、社会として「排除を許さない」というメッセージになります。制度は心を直接変えることはできませんが、「こういう社会を目指している」という意思を表すことはできます。
そして何より大切なのは、私たち一人ひとりが「自分も無意識に差別していないか」と問い続ける姿勢です。「あの人は外国人だから」「言葉が通じないから」ではなく、「同じ地域で生きる仲間」として出会う視点を持てるかどうか。その繰り返しの中でしか、壁は少しずつ崩れていかないのかもしれません。
分断を超える社会は、一朝一夕にはできません。しかし、目の前にいる「この人」との関係性からしか始められないこともまた、確かな現実です。誰かを排除することが自分の安心につながるのではなく、誰かとつながることが、自分の心を守ることにつながる――そんな実感が広がる地域を、私たちは目指していくべきなのではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。