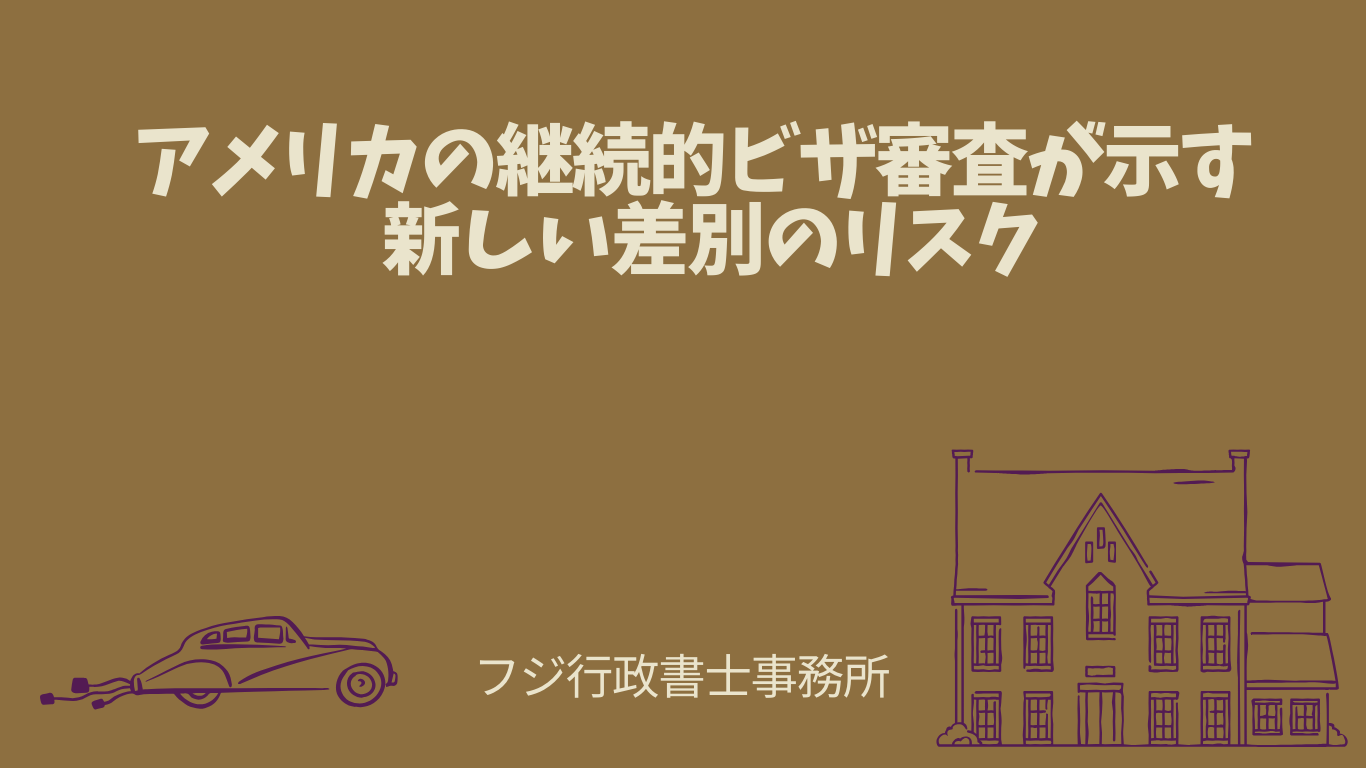監視が生む安心と不安――アメリカの新制度の二面性
アメリカ政府が導入を進めている「継続的審査」は、外国人に対する管理のあり方を根本的に変えるものです。これまではビザを取得すれば一定期間は比較的安定して滞在できると考えられてきました。しかし、新制度では「入国後も常に監視され続ける」という現実が突きつけられます。
確かに、この制度は治安の維持や不法滞在の防止という点で効果的です。犯罪やテロに結びつくリスクを早期に発見し、社会不安を抑える狙いがあります。国民に安心感を与えるという意味でも、多くの人に支持されやすい仕組みだといえるでしょう。
一方で、この監視体制は「安心」と同時に「不安」も生み出します。監視の対象となるのは外国人であり、「外国人だから常に疑われる」という構図が形成されかねません。外国人自身にとっては「信用されていない存在」として扱われることになり、心理的な負担が大きくのしかかります。社会全体からも「常に見張られている人」と見なされることで、生活の中に孤立感が広がる危険性があるのです。
つまり、制度は国民に安心をもたらす一方で、外国人には不安と不信感を強めるという二面性を持っています。このバランスをどう取るかが、大きな課題となるのです。
公平性の名の下に起きる「国籍フィルター」
アメリカ政府は、継続的審査を「すべてのビザ保持者に平等に適用する」と説明しています。表向きは公平であり、差別的ではないように見えます。しかし実務の場面では、国によって厳しさが異なる「国籍フィルター」が働く可能性があります。
たとえば、安全保障上の懸念が強い国や、過去にテロ組織との関係が指摘された国の出身者は、より厳しいチェックを受けるでしょう。一方で、経済的・政治的なパートナー国の出身者は比較的緩やかな扱いを受けるかもしれません。制度そのものは「全員対象」でも、運用の現場では国ごとの温度差が生まれやすいのです。
こうした「国籍フィルター」は、外国人本人の行動や努力とは無関係に差別を生み出します。真面目に生活していても、「その国の出身だから」というだけで疑われやすくなる。これは制度の公平性を損なうだけでなく、社会に偏見を根づかせることになります。
さらに、この構造は一度強まると固定化されやすい特徴があります。特定の国の出身者が不利に扱われることが当たり前になると、雇用や教育、住居の場面でも「その国の人は問題を起こす可能性がある」という偏見が広がりかねません。こうして、制度が差別の温床になる危険性が高まるのです。
日常生活に現れる新しい差別のかたち
監視体制が強まれば、外国人の生活に具体的な影響が出てきます。それは目に見える差別だけではなく、日常のさまざまな場面にじわじわと浸透していくものです。
まず、就職の場面です。企業にとって人材採用はリスク管理の一部でもあります。外国人が「継続的に監視され、場合によってはビザが突然取り消される可能性がある」と考えれば、採用をためらう企業が増えるかもしれません。「優秀な人材でもリスクが高い」という理由で不採用になることは、事実上の差別といえます。
次に、住居の場面です。貸主が「外国人は監視対象だからトラブルの原因になるかもしれない」と判断すれば、賃貸契約を断られる可能性があります。すでに外国人が住居探しで苦労する事例は多く報告されていますが、制度が強化されれば、その傾向はさらに強まるでしょう。
教育の場面でも影響が懸念されます。子どもが「監視対象の家庭の子」と見なされれば、同級生や保護者の間で偏見が生まれるかもしれません。子ども本人に何の責任もないのに、家庭の背景によって差別を受けるのは大きな問題です。
さらに、SNS上での発言が誤解されるリスクもあります。言語や文化の違いから、本来は軽い冗談や日常的な不満が、過激思想や反体制的な発言とみなされる可能性があります。こうした誤解が積み重なることで、外国人が自由に意見を述べること自体が難しくなる恐れがあります。
これらはすべて「目に見えにくい差別」ですが、外国人の日常生活に大きな影響を与えます。監視制度は安全を守るためのものとして導入されても、その副作用として新しい差別の形を生み出しかねないのです。
共生社会を守るために必要な視点
では、こうした差別のリスクをどう防ぐべきでしょうか。
第一に求められるのは、制度の透明性です。どのような行為が違反とされ、どのような基準で判断されるのかを明確に示すことが不可欠です。基準が不透明であれば、外国人は「何をしても疑われる」という不安を抱き、社会全体にも「外国人は危険だ」という偏見が強まります。
第二に、公平性の実効性を確保することです。制度の表向きの説明だけでなく、実務においても国籍や出身地域によって扱いを変えないことが重要です。国籍ではなく、本人の行動や生活状況に基づいて判断される仕組みを整える必要があります。
第三に、外国人自身の声を反映させることです。制度設計や運用において、当事者である外国人や支援団体の意見を取り入れることで、不公平感を和らげ、制度への理解を深めることができます。外国人が「一方的に監視される存在」ではなく「社会の一員として尊重される存在」であることを示すことが大切です。
最後に、受け入れる社会の姿勢が問われます。外国人を「リスク要因」として排除するのではなく、共に生活し働く仲間として認めることが必要です。制度が導入されても、社会の意識が変わらなければ差別はなくなりません。むしろ制度の存在を理由に差別が正当化される危険すらあります。だからこそ、制度と同時に教育や情報発信によって偏見をなくす努力が欠かせません。
おわりに
アメリカの継続的審査は、治安維持や不法滞在防止の観点からは有効な制度です。しかしその裏には、「外国人は常に疑われる存在」という新しい差別のリスクが潜んでいます。監視体制が強化されればされるほど、外国人の生活の中に孤立感や不安が広がり、共生社会から遠ざかる危険性があるのです。
安全と自由、治安と共生。この二つをどう両立させるかは、アメリカだけでなく、日本を含む多くの国にとって避けて通れない課題です。制度を導入する際には、透明性と公平性を徹底し、外国人を尊重する社会の姿勢を持つことが何よりも大切です。
新たな差別を生み出さないために、私たちには制度の効果だけでなく、その副作用にも目を向ける冷静さが求められています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。