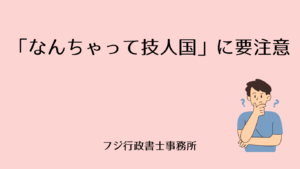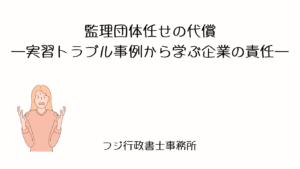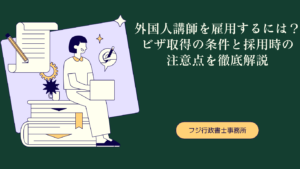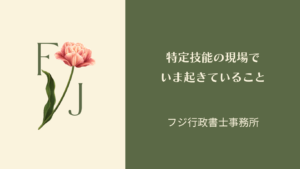監理団体任せにしない!企業主導で行う技能実習の管理とは
技能実習制度は、外国人材に日本の技能や知識を習得してもらい、母国の発展に活かしてもらうことを目的とした制度です。しかし、実際の現場では「人手不足の補填策」としての側面が強く、制度の理念と企業の実情の間にギャップがあることも少なくありません。制度上、実習を行うのは「実習実施者」である企業であり、監理団体はその支援や監督を担う立場です。ところが、実際には多くの企業が監理団体に任せきりにしてしまい、制度理解や書類対応が不十分なまま運用されているケースが目立ちます。
監理団体に頼り切りの姿勢は、一見すると効率的に見えますが、実は企業側のリスクを高める要因にもなります。例えば、OTIT(外国人技能実習機構)による実地調査や審査の際、最終的な責任を問われるのは企業側です。書類の不備や実習内容の齟齬が発覚すれば、技能実習計画の認定取消しや受入れ停止などの重大な処分につながる可能性もあります。制度が大きく変わろうとしている今だからこそ、企業が主体的に制度運用を理解し、自社の実習生をしっかり管理する体制を整えることが重要です。
「良好な修了」が企業の信用を左右する
近年、技能実習2号を修了した外国人材が特定技能制度に移行するケースが増えています。この移行の際に必須とされるのが「良好な修了」です。良好な修了とは、単に期間を満了したというだけではなく、実習の成果や勤務態度が一定の基準を満たしていることを証明するものです。
良好な修了と認められるためには、まず技能実習期間が2年10ヶ月以上であることが必要です。その上で、以下のいずれか1つの書類を提出する必要があります。
- 技能検定3級(実技試験)の合格証明書の写し
- 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習生に関する評価調書
これらの証明書類は、実習生の努力や成果だけでなく、企業側がきちんと教育・管理を行っていたかどうかの証拠にもなります。監理団体が試験の申込や評価調書の作成をサポートすることはありますが、日々の実習内容や勤務状況、出勤記録の管理は企業にしかできません。つまり、良好な修了を得られるかどうかは、企業の管理体制に大きく左右されるのです。
特定技能への移行は、企業にとってもメリットがあります。特定技能人材として再び受け入れることで、すでに職場に慣れた即戦力を確保でき、人材不足の解消にもつながります。逆に、管理がずさんで良好な修了が得られなければ、実習生本人の進路を閉ざすだけでなく、企業の評判にも影響しかねません。
日々の実務管理が鍵になる
制度対応で最も重要なのは、日々の現場での管理をいかに丁寧に行うかという点です。技能実習の現場では、単に働いてもらうだけではなく、「実習」として記録や計画と整合させていくことが求められます。以下のようなポイントを意識しておくと、後々のトラブル防止につながります。
まず、出勤簿や実習記録の正確な管理は基本中の基本です。残業時間や休日労働の扱いについても、労働基準法と技能実習計画の両面から整合を取る必要があります。OTITの実地調査では、タイムカードや勤務表の照合が行われるため、実態と記録がずれていると重大な指摘を受けることになります。
次に、実習計画と実際の業務内容の乖離を防ぐことも重要です。例えば、計画上は「溶接技術の習得」となっているのに、実際には単純な部品の移動や清掃ばかりをさせていると、計画違反とみなされる可能性があります。現場の担当者にも制度の基本的な内容を理解してもらい、日常的に実習計画に即した業務を行えるよう意識づけをすることが必要です。
また、日本語教育や生活支援の体制も企業の評価に影響します。日本語能力が伸びないまま実習期間を終えると、技能検定や評価試験の受験自体が難しくなることもあります。監理団体任せにせず、企業内での日本語学習の時間確保や、地域の日本語教室との連携など、主体的な支援を組み込むことで、実習生の定着率や評価も高まります。
制度転換期に備えた企業の体制づくり
技能実習制度は、2027年度を目途に「育成就労制度」へと移行する予定です。新制度では、より実践的な人材育成と就労への移行を重視する仕組みとなり、企業にもこれまで以上に明確な責任が求められます。つまり、従来のように監理団体に任せておけばよいという姿勢では通用しなくなります。
新制度では、日本語能力の向上支援やキャリア形成支援が重要な要素となる見込みです。また、育成就労を経て長期的に働き続ける外国人材が増えることも想定されます。これまで技能実習を「3年間の一時的な受け入れ」と考えていた企業も、今後は長期的な人材戦略として制度に向き合う必要が出てくるでしょう。
そのためには、企業内に制度理解と運用のノウハウを蓄積することが欠かせません。担当者を固定して制度研修を受けさせる、実習生管理のマニュアルを整備する、日本語教育や生活支援の外部連携先を確保しておく、といった準備を進めておくことで、新制度への移行もスムーズになります。監理団体と協力しつつも、主導権は企業が握るという姿勢が求められます。
まとめ
技能実習制度の運用において、監理団体の存在は欠かせません。しかし、最終的な責任を負うのはあくまで実習実施者である企業です。制度変更が進む中で、企業が主体的に制度を理解し、日々の実務管理や支援体制を強化することが、結果的に自社の信用と人材確保につながります。監理団体任せの姿勢から一歩踏み出し、企業主導で技能実習制度に向き合うことが、これからの時代に求められる姿勢といえるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。