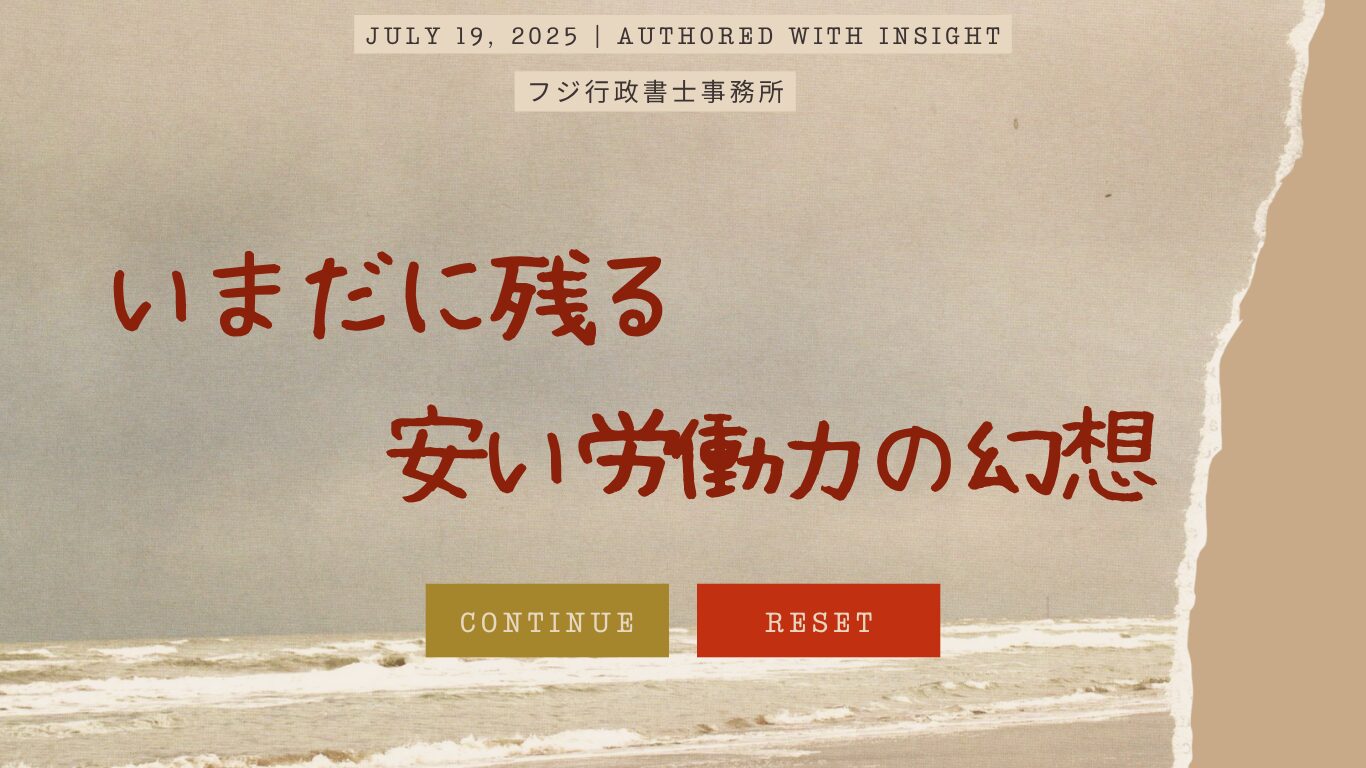外国人労働者の視点──「使い捨てではない私たち」
「私たちは、ただの労働力ではありません」。
ある外国人労働者がそう語ったとき、彼がどれだけの努力と苦労を経て日本にたどり着いたのか、思いを馳せずにはいられません。日本で働く外国人の背景は多様です。大学を卒業して正社員として採用された人、特定技能として現場で即戦力として期待されている人、留学しながらアルバイトをして生活費を支える人、あるいは永住者・定住者として長年日本で暮らしている人など、その立場も経緯もさまざまです。
しかし、いずれの立場にあっても、職場において「外国人だから」という理由で不平等な扱いを受ける事例は、依然として少なくありません。たとえば、日本人と同じ業務内容にもかかわらず賃金が低かったり、正当な昇進機会が与えられなかったり、日本語力を理由に職務を限定されたりする現実があります。さらには、残業代の未払いや有給休暇の取得妨害、職場での孤立やハラスメントなど、構造的な問題が絡んでいるケースもあります。
とくに深刻なのは、「声を上げにくい」状況が依然として放置されていることです。在留資格の維持が雇用に依存している場合、理不尽な状況にあっても「言ったら解雇されるかもしれない」「契約を切られて帰国させられるのでは」と不安になり、誰にも相談できないまま耐えてしまう――そのような事例は今も多数存在します。
外国人労働者が求めているのは、特別扱いではありません。ただ、同じ職場で働く者として、正当に評価され、対等に尊重されたいという、極めてまっとうな願いです。安価な労働力としてではなく、同じ社会を生きる仲間として、日本社会がどれだけ真剣に向き合えるかが、今まさに問われています。
経営者の視点──「安く雇える」は本当に得なのか?
「人手が足りない。けれどもコストはかけられない。だから外国人を雇う」。
そういった判断をする中小企業経営者は少なくありません。たしかに、多くの業種では人手不足が深刻です。とくに建設、介護、製造、飲食、清掃といった現場労働においては、求人を出しても日本人が集まらず、結果として外国人に頼らざるを得ないという状況が日常化しています。
しかし、そこで外国人を「安価な労働力」とみなしてしまうと、経営は根本から崩れ始めます。まず、在留資格制度の制約があります。特定技能や技術・人文知識・国際業務など、それぞれの在留資格には許可されている職務内容が厳格に定められており、業務との不一致は不法就労や在留資格取消のリスクを伴います。
また、外国人労働者側ももはや「安くても我慢する存在」ではありません。インターネットやSNSの普及により、自身の権利や法制度についての情報が容易に手に入り、不当な扱いに対する知識と意識が確実に高まっています。待遇に不満があれば、同業他社に移る、あるいは帰国して別の道を選ぶことも珍しくありません。つまり、安く使い捨てるような雇用は、定着率の低下や企業イメージの悪化、ひいては事業継続そのもののリスクに直結します。
むしろ、外国人を中長期的な戦力として捉え、日本語教育の支援、評価制度の明確化、多文化理解の研修などに投資する企業のほうが、優秀な人材の定着に成功しています。「安さ」で集めた人材はすぐに去り、「信頼」で集めた人材は根づく――その違いを、経営者が真に理解しなければ、今後の労務管理は立ち行かなくなるでしょう。
行政書士の視点──「制度の誤解」が招く現場の混乱
外国人雇用において、最も見落とされがちなのは「制度を正確に理解していないまま採用を進めてしまう」ことです。行政書士として現場に立つたびに、あまりに多くの事業者が在留資格や労働関連法令について誤解を抱いたまま雇用に踏み切っていることを痛感します。
たとえば、技術・人文知識・国際業務のビザで倉庫作業をさせていたり、週28時間の制限がある留学生にフルタイム勤務をさせていたり、在留資格の更新や変更に必要な書類の準備を怠っていたりといった例が後を絶ちません。こうした運用は、企業にも外国人本人にも大きなリスクとなり、最悪の場合は資格取消・退去強制・刑事罰といった事態にもつながりかねません。
また、労働条件通知書や契約書が不備だったり、就業規則に外国人への配慮が全く盛り込まれていなかったりするケースも珍しくありません。「監理団体に任せているから大丈夫」「役所が教えてくれるはず」と誤信している事業者も多いのが実情です。
行政書士として私たちができるのは、申請業務を代行するだけでなく、制度の背景や現場への影響まで丁寧に伝え、事業者が“制度の内側”から正しく行動できるよう伴走することです。外国人雇用は「書類を出せば終わり」ではなく、「雇ったその日からが始まり」だという認識が必要です。今後ますます制度が複雑化する中で、企業と外国人の双方を守る専門家の存在が、これまで以上に重要になるでしょう。
国の視点──共生か、分断か。問われるのは社会の意思
国としての姿勢もまた、転換点を迎えています。
特定技能制度の創設や、技能実習制度の廃止・再編検討、永住申請要件の厳格化など、外国人受け入れ政策は大きな見直しの時期に入っています。しかし、その方向性が「人手不足解消のための短期的手段」にとどまってしまえば、やがて制度疲労を起こし、社会全体にひずみが広がることは避けられません。
今後、問われるのは「どんな社会をつくりたいのか」という国家としての意思です。外国人を一時的に使って終わる“労働資源”として扱うのか、それとも、日本社会の一員として迎え入れ、教育・医療・住宅・子育て・地域活動などあらゆる場面で支え合う“共生のパートナー”として位置づけるのか。選択を迫られています。
たとえば、外国にルーツを持つ子どもたちの就学支援や、多言語による行政サービス、災害時の情報提供、医療通訳体制の整備など、生活インフラの整備が国レベルで急がれます。
さらに、優良な受け入れ企業を評価・認定する制度、地方自治体との連携強化、そして外国人当事者の声を政策に反映する仕組みなど、「外国人とともに生きる」国づくりが求められています。
共生か分断か――それは制度の問題ではなく、社会全体の意思決定です。
今こそ、「安い労働力」という幻想を脱し、国家としての覚悟をもって、新たな社会のビジョンを示すときです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。