外国人とふるさと納税——誤解と真実
日本に中長期で滞在する外国人にとって、税金は生活の中でもっとも大きな不安要素の一つです。給料から控除される住民税や所得税、そして年金や社会保険料。これらは日本人にとっても分かりにくい仕組みですが、言語や文化の壁を抱える外国人にとっては、さらに理解が難しいものです。その中でも近年関心が高まっているのが「ふるさと納税」です。テレビやインターネットでしばしば話題になる制度であり、返礼品としてお米や肉、果物や旅行券などがもらえることから、日本人にはすっかり定着しています。しかし外国人の多くは、「自分には関係ない制度だ」と思い込んでいます。
本稿では、外国人がふるさと納税をめぐって抱いている誤解の実態と、その背後にある心理や制度的背景を掘り下げます。そして、実際には利用できる制度であること、そのために必要な条件や注意点、さらにはふるさと納税が外国人にとってどのような意味を持つのかを、多角的に考えていきます。
誤解が生まれる背景と実態
外国人がふるさと納税を利用しない最大の理由は、「自分には権利がない」と思い込んでいるからです。国籍にかかわらず利用可能であるにもかかわらず、なぜそのような誤解が広まってしまうのでしょうか。
第一に、日本語の壁があります。ふるさと納税の仕組みを説明する公式サイトやポータルサイトの多くは日本語のみで書かれており、英語や中国語、ベトナム語などの案内は限られています。制度の根本に「寄附」という概念があり、さらに税金の控除と絡めて説明されるため、日本語が得意な人でなければ理解するのは容易ではありません。
第二に、「納税」という言葉の持つイメージです。外国人にとって「納税=日本人の義務」という感覚が強く、「自分は日本国籍ではないから対象外だろう」と直感的に考えてしまいます。この思い込みは非常に根強く、同僚や友人が利用している姿を見ても「自分にはできない」と判断してしまうのです。
第三に、情報格差です。日本人であれば勤務先や家族を通じてふるさと納税の情報に触れる機会がありますが、外国人はそのようなつながりが弱い場合が多く、正しい情報を得られないまま誤解を抱き続けることになります。会社の人事担当者が外国人従業員にふるさと納税を案内することはほとんどなく、学校でも説明はされません。結果として、周囲に相談できず孤立した状態で制度から取り残されてしまいます。
実際の声としては、「同僚は毎年お米をもらっているのに、自分はできないと思っていた」「日本語のサイトで申し込みしようとしたが途中で断念した」「ビザ更新に影響が出るのではと不安で利用を控えた」などが挙げられます。これらは誤解や不安によって制度を活用できず、せっかくの機会を逃してしまった例といえるでしょう。
制度の仕組みと正しい理解
誤解を解くためには、ふるさと納税の仕組みを正しく理解する必要があります。ふるさと納税は「寄附制度」であり、寄附先の自治体を選んで寄附を行い、その金額の一部が翌年の所得税や住民税から控除される仕組みです。つまり、国籍の有無は一切関係なく、日本に住所を持ち、所得税や住民税を納めている人なら誰でも利用できます。
利用の流れはシンプルです。インターネットのポータルサイトや自治体の窓口を通じて寄附を行い、返礼品を受け取り、年末調整または確定申告で控除申請を行います。ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要になる場合もあり、手続きの負担は比較的軽いといえます。
ここで重要なのは「税金を納めていること」です。留学生でアルバイト収入しかなく、所得が一定額に満たない場合は税控除の効果が小さい、あるいはまったく得られない可能性があります。一方で、就労ビザで働いている人や、配偶者ビザ・永住権を持っている人は、給与から住民税や所得税が引かれていることが多く、十分に控除を活用できます。
ふるさと納税は寄附先を自由に選べる点も特徴です。出身地や縁のある地域、日本で暮らしている街などを応援でき、単なる節税手段にとどまらず、地域社会とのつながりを感じられる制度です。外国人にとっても「自分が日本社会に貢献している」という実感を持てる点は大きな意味を持つでしょう。
外国人が直面する具体的な障害
制度的には利用可能であるにもかかわらず、外国人がふるさと納税を活用できないのは、実務的な障害が多いからです。
最も大きいのは言語の壁です。ふるさと納税のポータルサイトはほとんどが日本語表記であり、手続きの流れを理解するのが難しいと感じる外国人は少なくありません。返礼品の選択や配送先の入力、クレジットカード決済の画面もすべて日本語で表示されるため、途中で諦めてしまうケースがあります。
次に、マイナンバーや身分証明の提出に対する不安です。ふるさと納税では控除申請のためにマイナンバーカードや通知カードのコピーが必要になりますが、外国人の中には「入管に情報が伝わるのでは」「ビザ更新に悪影響があるのでは」と心配する人もいます。こうした不安は制度に対する理解不足から生じていますが、心理的な障壁としては無視できません。
さらに、返礼品の配送トラブルもあります。たとえば、契約している賃貸住宅で表札が日本語と異なっている場合、荷物が届かないことがあります。外国人の名前表記が漢字とアルファベットで異なるために受け取りがスムーズにいかないこともあります。こうした細かい問題が積み重なり、「面倒だから利用しない」という判断につながっているのです。
また、制度を正しく利用するためには年末調整や確定申告が必要になる場合がありますが、日本語の書類に不慣れな外国人にとっては大きなハードルです。会社がワンストップ特例の申請をサポートしてくれない場合、自分で書類を理解し提出しなければならず、「結局は専門家に頼るしかない」と感じる人も少なくありません。
活用のための工夫と社会的意義
これらの障害を乗り越え、外国人がふるさと納税を安心して利用するためには、いくつかの工夫が考えられます。
第一に、自治体やポータルサイトが多言語での案内を充実させることです。英語や中国語、ベトナム語で基本的な説明や手続きガイドを提供すれば、多くの外国人が「自分にもできる」と気付くきっかけになります。
第二に、勤務先や学校での情報提供です。日本人社員と同様に外国人従業員に向けて説明会や資料を配布すれば、誤解を防ぐことができます。実際に「会社からふるさと納税を紹介されて初めて知った」という外国人もおり、身近な環境からのアプローチが効果的です。
第三に、専門家のサポートです。行政書士や税理士などが外国人向けに分かりやすい解説や手続きをサポートすれば、安心して制度を活用できます。特に、扶養控除や配偶者控除とあわせて税全体の仕組みを整理してもらうことで、ふるさと納税の効果をより大きく実感できるでしょう。
そして最後に、ふるさと納税の持つ社会的意義を再認識することが大切です。税金は外国人にとって「義務」や「負担」というイメージが強いですが、ふるさと納税は「日本社会に関わり、地域を応援する」ための手段です。外国人がこの制度を活用することで、生活の中に楽しみが増えるだけでなく、日本社会に参加している実感を持つことができます。
このように、ふるさと納税を通じて外国人が税制度に積極的に関わることは、共生社会の実現に向けた大きな一歩になるといえます。
まとめ
ふるさと納税は、本来であれば国籍に関係なく誰でも利用できる制度です。しかし現実には、外国人の多くが「自分にはできない」と思い込み、利用しないまま過ごしています。その背景には日本語の壁や情報不足、不安や誤解があり、実際の障害となっています。
正しい理解を広め、利用を後押しすることは、外国人にとって生活を豊かにするだけでなく、日本社会との距離を縮めることにもつながります。返礼品を受け取り、地域を応援するという仕組みは、単なる節税手段を超えて「共に生きる社会」の象徴ともいえるでしょう。
中長期滞在の外国人がふるさと納税を正しく理解し、自信を持って活用できるようにすること。それは、外国人自身の生活の安定と満足を高めるだけでなく、日本社会全体にとっても大きな意味を持つのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
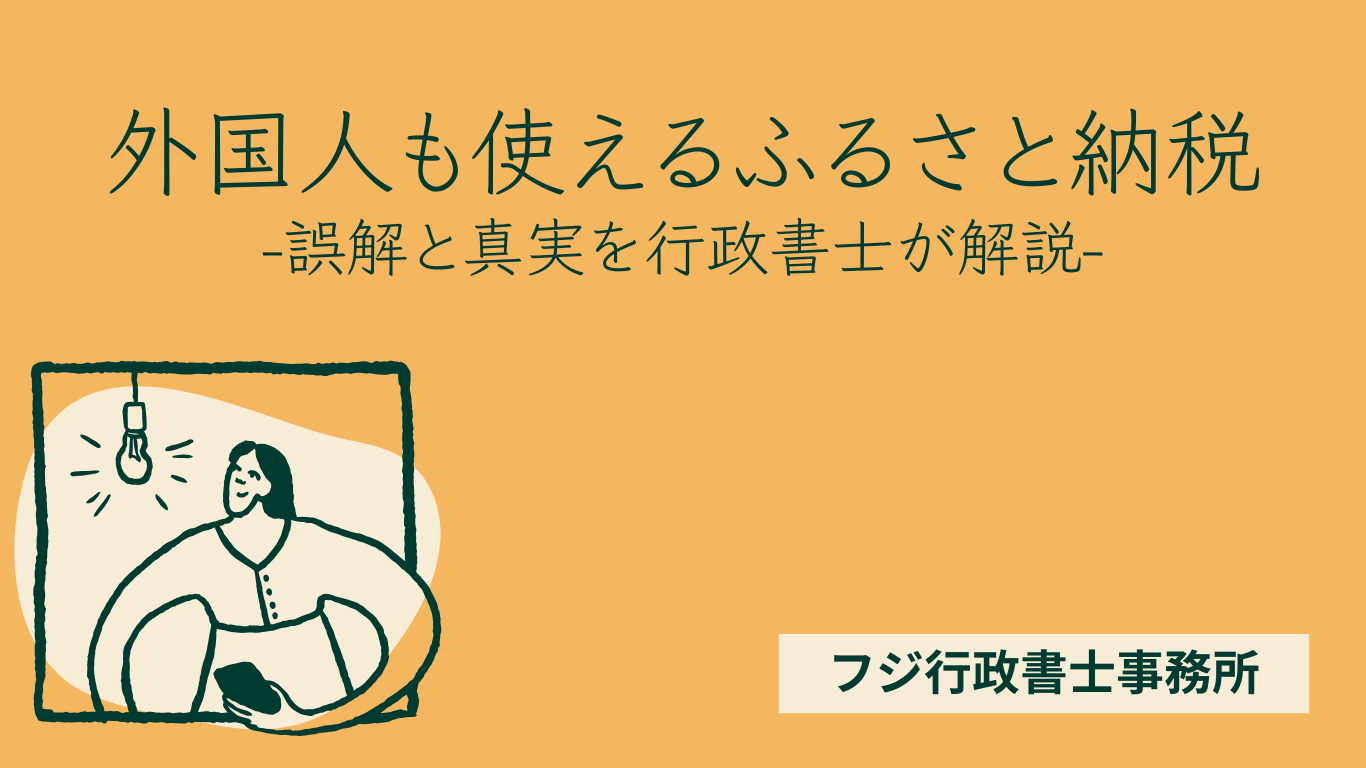
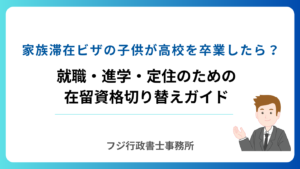







コメント