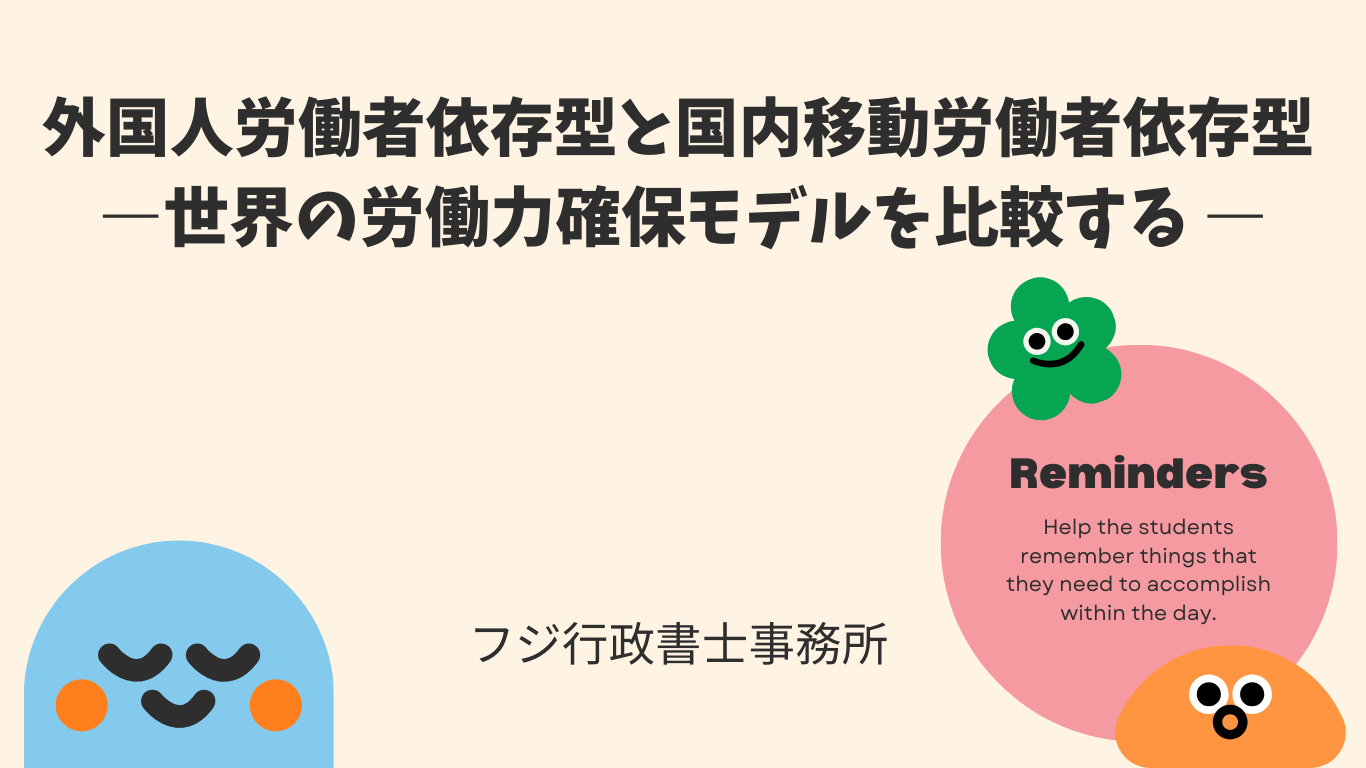外国人労働者依存型と国内移動労働者依存型――世界の労働力確保モデルを比較する
近年、多くの国々が人口動態の変化や産業構造の転換により、深刻な人手不足に直面しています。その対応策として、国ごとに異なる「労働力確保のモデル」が存在します。大きく分けると、外国人労働者を積極的に受け入れて経済を支える「外国人労働者依存型」と、国内の人口移動によって人手を確保する「国内移動労働者依存型」の二つです。
外国人労働者依存型の代表例はシンガポール、香港、台湾、そして日本です。シンガポールでは総人口の約3割が外国人で、建設業や介護、家事労働などは外国人なしでは成立しません。香港では60万人以上の外国人家事労働者が都市生活を支えています。台湾も同様に、製造業や介護の現場で外国人比率が急速に高まっています。そして日本は200万人を超える外国人労働者を抱え、技能実習や特定技能制度を通じて、農業、建設、介護、外食など幅広い分野で依存を強めています。
これらの国々は、もはや「外国人前提」の社会を構築しており、外国人なしでは経済活動の維持が困難です。背景には出生率の低下と高齢化があります。例えば日本は出生率が1.2程度、シンガポールはさらに低い1.0前後であり、労働人口を国内だけで賄うことが不可能となっています。
国内移動労働者に依存する国々
一方で、中国やインドのように外国人を大量に受け入れるのではなく、国内の人口移動によって労働力不足を補ってきた国々も存在します。これを「国内移動労働者依存型」と呼ぶことができます。
中国では「農民工」と呼ばれる出稼ぎ労働者が約3億人存在し、都市部の建設業や製造業を支えています。彼らは農村部に戸籍を持ちながら都市で働くため、教育や医療などの社会保障面で不利な立場に置かれることが多く、格差問題が深刻化しています。外国人労働者の比率はごく小さく、専門職や教育分野を除けばほとんど受け入れていません。
インドも同様で、国内に1億人を超える出稼ぎ労働者が存在します。農村から都市への人口流動は経済成長を下支えしていますが、労働者の生活は不安定で、社会保障の整備は遅れています。インドネシアも国内島嶼間の移動で都市部の労働力を確保しており、外国人労働者の比率は低い水準にとどまっています。
さらにフィリピンは少し特殊です。国内の農村から都市への出稼ぎと同時に、国外への出稼ぎ(OFW=海外フィリピン労働者)が経済の基盤となっており、年間の海外送金額はGDPの1割を超える規模に達しています。これは「国内移動依存」と「国外輸出依存」が組み合わさった独自のモデルです。
アフリカでもナイジェリアやエチオピアといった人口大国は、外国人労働者の受け入れは限定的で、農村から都市部への国内出稼ぎが経済の要となっています。これらは「中国型」の特徴を持ち、外国人労働者に頼らないまま成長を続けてきました。
二つのモデルの比較と課題
外国人労働者依存型と国内移動依存型の最大の違いは、労働力を国外に求めるか、国内に求めるかです。前者は外国人を制度的に組み込み、多文化共生や移民政策を不可避の課題として抱えます。後者は外国人をほとんど受け入れない代わりに、国内格差を前提とした出稼ぎ移動を維持する必要があります。
外国人依存型の課題は、社会統合と権利保護です。シンガポールでは外国人と市民の居住空間や教育機会が分断されており、香港でも外国人労働者が差別的扱いを受けることがあります。日本も外国人労働者を「一時的な存在」と見なす風潮が根強く、長期的な共生政策はまだ整備途上です。
国内移動依存型の課題は、国内格差の固定化と労働者の不安定な生活です。中国の農民工は都市に不可欠な存在でありながら、教育・住宅・社会保障において都市戸籍の住民と大きな差があります。インドの出稼ぎ労働者も同様に、災害や経済危機の際に真っ先に打撃を受けます。これらは国内の統合を脅かす要因となっています。
両モデルとも限界を抱えています。外国人依存型は社会統合に失敗すれば分断を生み、国内移動依存型は人口減少が進めば内需だけでは労働力不足を補えません。AIや自動化が一部の人手不足を解消するとしても、すべてを代替することは難しいのが現実です。
世界の労働力確保モデルの行方
今後の世界では、外国人依存型の国々も国内移動依存型の国々も、労働力確保の戦略を柔軟に変化させる必要があります。シンガポールは高度人材をさらに重視し、単純労働の比率を減らす方向に動いています。台湾は介護や農業分野で外国人に依存し続ける一方、技術人材の呼び込みを強化しています。日本も特定技能制度の拡充や永住権の緩和といった政策転換を迫られています。
一方、中国やインドも例外ではありません。中国は少子高齢化が急速に進み、今後は国内の農民工だけでは労働力不足を解決できなくなる可能性があります。インドも出生率は下がりつつあり、人口ボーナスが永遠に続くわけではありません。いずれは外国人受け入れを検討する局面が訪れるかもしれません。
日本にとって重要なのは、この二つのモデルの「良い部分」を学び、自国に適合させることです。外国人を前提に制度を設計しながらも、中国のように国内の潜在的労働力を活用する視点を忘れないこと。短期的な人手不足解消にとどまらず、長期的な社会統合を視野に入れた制度設計が求められます。
世界の労働力確保モデルは二分法ではなく、多様な形に収束していくでしょう。外国人労働者依存型と国内移動労働者依存型の双方が限界に直面する時代において、持続可能な共生の仕組みを構築することが、21世紀の最も大きな課題の一つなのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。