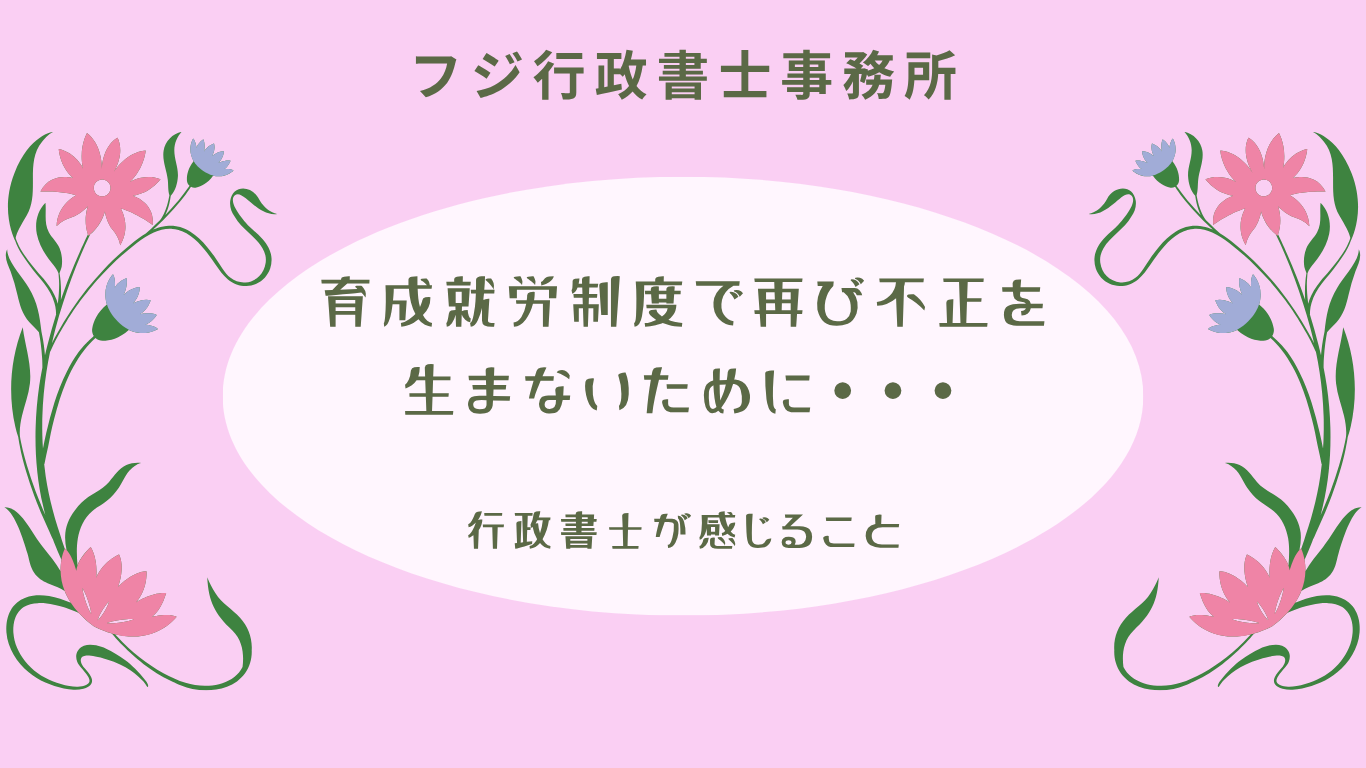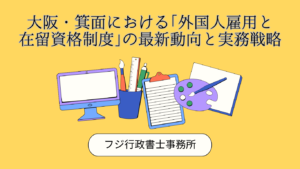新制度移行の背景と狙い(行政書士として見える現場)
行政書士として、日々、外国人雇用と在留資格に関する相談を受けています。少子高齢化と人手不足が重くのしかかる中、製造業・介護・農業・建設などでは外国人材が欠かせない存在になりました。他方で、これまで中核だった技能実習制度は、「人材育成」を掲げながらも、低賃金労働力の確保へと目的がずれ、転籍の厳格制限や劣悪な労働環境、失踪といった問題を繰り返してきました。私の事務所にも、契約内容と実態の乖離に悩む当事者や、「制度の枠内でどう対応すべきか」と問う受入企業が相次いでいます。
こうした反省の上に、2024年に成立した法改正は技能実習の廃止と「育成就労制度」創設を柱とし、日本語能力と技能水準の向上を前提に、特定技能への円滑な移行を目指します。一定条件の下で1〜2年後に転籍が可能となり、監理団体に代わって「監理支援機関」が導入され、外部監査人の関与など監督の強化も図られます。制度の設計思想は、短期の穴埋めから中長期の定着へ。育成就労(最大3年)から特定技能1号(通算5年)、さらに2号や永住へと展望が開く構造です。
もっとも、制度が切り替わる局面では、新たな不正や中間搾取の余地が必ず生まれます。私は現場での経験から、導入初期ほど監督と摘発の「前例」が不足し、グレーゾーンを狙う動きが顕在化しやすいことを繰り返し目にしてきました。改革の理念を実装へと落とし込むには、事業者・監理支援機関・本人・専門職の四者が、具体的な手順と記録で運用を固めることが不可欠です。
新制度で顕在化しうる不正と闇のパターン
第一に、転籍制度の悪用です。本来はミスマッチ解消の安全弁ですが、悪質な仲介者が介在すると、「採用直後に教育名目で受け入れ→短期で高条件の他社へ転籍」という流れに手数料ビジネスが生まれます。結果として育成コストの回収ができず、現場は短期回転の人材争奪に陥ります。私は特定活動系の緩やかな枠組みで類似の構図を見たことがあり、転籍申出の理由書・面談記録・労働条件通知の差分など、証拠の整備が緊要だと痛感しています。
第二に、名義貸し・架空雇用の横行です。実働のない雇用契約で在留資格だけを取得させ、実際は別の職場や職種で働かせる手口は、制度が変わっても形を変えて現れます。相談の際には既に在留取消や退去強制のリスクが迫っていることも少なくありません。雇用契約書・シフト・勤怠・賃金台帳・社会保険の加入実績といった一次資料の整合性確認を、申請前からセットで行う体制が必要です。
第三に、留学からの不正移行です。学業の実態が希薄なまま日本語学校在籍中に育成就労や特定活動へ切り替え、実質的に就労目的化するケースです。監理支援機関や受入側が形式を整えると、外形的には適正に見えて発見が遅れます。学校側の出席・成績データ、生活実態の聞き取り、アルバイトの範囲や時間の検証を含む立体的な審査が求められます。
第四に、監理支援機関の質のばらつきです。書類審査を通るだけで実質支援が空洞化した「名ばかり監理」が再来する恐れは現実的です。私は受入企業からの相談時、支援計画の実施体制(講師配置、言語支援、相談窓口、緊急対応)や、前期のKPI(離職率、転籍理由、相談件数と解決までの所要日数)を確認し、数値で伴走実績が語れるかを見ます。ここが曖昧な機関は、トラブル時に対応が遅れがちです。
なぜ不正が生まれるのか(構造的要因の洗い出し)
導入初期の「監督より普及」が第一の要因です。制度の立ち上げは広報・登録・審査ラインの整備が先行し、是正の前例や判例の蓄積が遅れます。ルールはあっても、現場は線引きの感覚を掴み切れていない。ここを悪質事業者は突きます。次に、言語・文化・手続の複雑さが、当事者の権利行使を難しくします。通訳を入れても、専門用語と様式の壁は厚く、気づかないうちに違反状態に陥ることがあるのです。
さらに、人手不足の常態化が「逸脱の容認」を生みます。現場は人員を確保することが最優先になり、契約・配置・時間管理の厳格運用がおろそかになる。賃金水準の低い分野ほど、短期転籍と条件上積みのインセンティブが強く働きます。最後に、監理支援機関の許可・外部監査の形式化です。チェックリスト適合は最低条件に過ぎず、支援の質(言語別相談の実効性、ハラスメント対応の迅速さ、生活支援の実装度)は、紙の上では測り切れません。実地の面談・現場観察・第三者評価との突き合わせが必要です。
行政書士としては、こうした構造要因を見越し、運用の初期から「証拠の作り方」を現場に根付かせることを重視します。採用決裁の根拠資料、配置理由、教育記録、面談メモ、労務トラブルの一次対応ログなど、後から検証可能な形で残す。最初の積み上げが、のちの紛争予防と更新審査の説得力を決めます。
不正防止の実務提案と、行政書士の具体的役割
実務で効く対策は、抽象的なポリシーではなく、日々の運用に仕込む「小さな仕組み」です。転籍対策なら、就労開始90日・180日の節目面談を定例化し、職務内容・教育進捗・評価・処遇を当事者と確認、合意内容を記録します。転籍申出が出た際は、理由書式を標準化して、配置変更や教育補強など代替案の提示と比較検討のログを残す。これが「真に本人の利益か」「育成目的に反しないか」を、後からも説明可能にします。
名義貸し防止には、雇用契約・労働条件通知・勤怠・賃金台帳・社保加入・現場写真・業務マニュアルのひとまとめ管理が有効です。申請段階から突合の前提を作り、更新・転籍・監査の各局面で同一セットを参照する運用にしておくと、虚偽や齟齬を早期に炙り出せます。留学からの不正移行には、学校側の出欠・成績に加え、生活費の出所、アルバイト時間の実測、授業時間との整合といった立体的確認が欠かせません。
監理支援機関の見極めは、提案書の美しさではなく、実績のデータです。月次相談件数、内容区分、解決所要日数、転籍理由のトップ3、離職後フォローの手順、24時間対応の実装度など、KPIが定義され、第三者が再検証できるか。私は受入企業の顧問として、支援機関との契約にKPI報告条項と違反時の是正・減額条項を組み込み、四半期レビューを行う条項例を提供しています。
行政書士が担うべきは、制度理解の翻訳者であり、記録と手続の設計者であり、初動対応の司令塔です。申請書が通るかどうかではなく、通った後に現場が崩れない仕組みを一緒に作ること。育成就労から特定技能への移行を見据え、要件整備のロードマップ(日本語・技能試験、評価記録、教育時間数、OJTログ)を最初から逆算して設計すること。制度は変わっても、実務の成否は「準備」と「記録」に尽きます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。