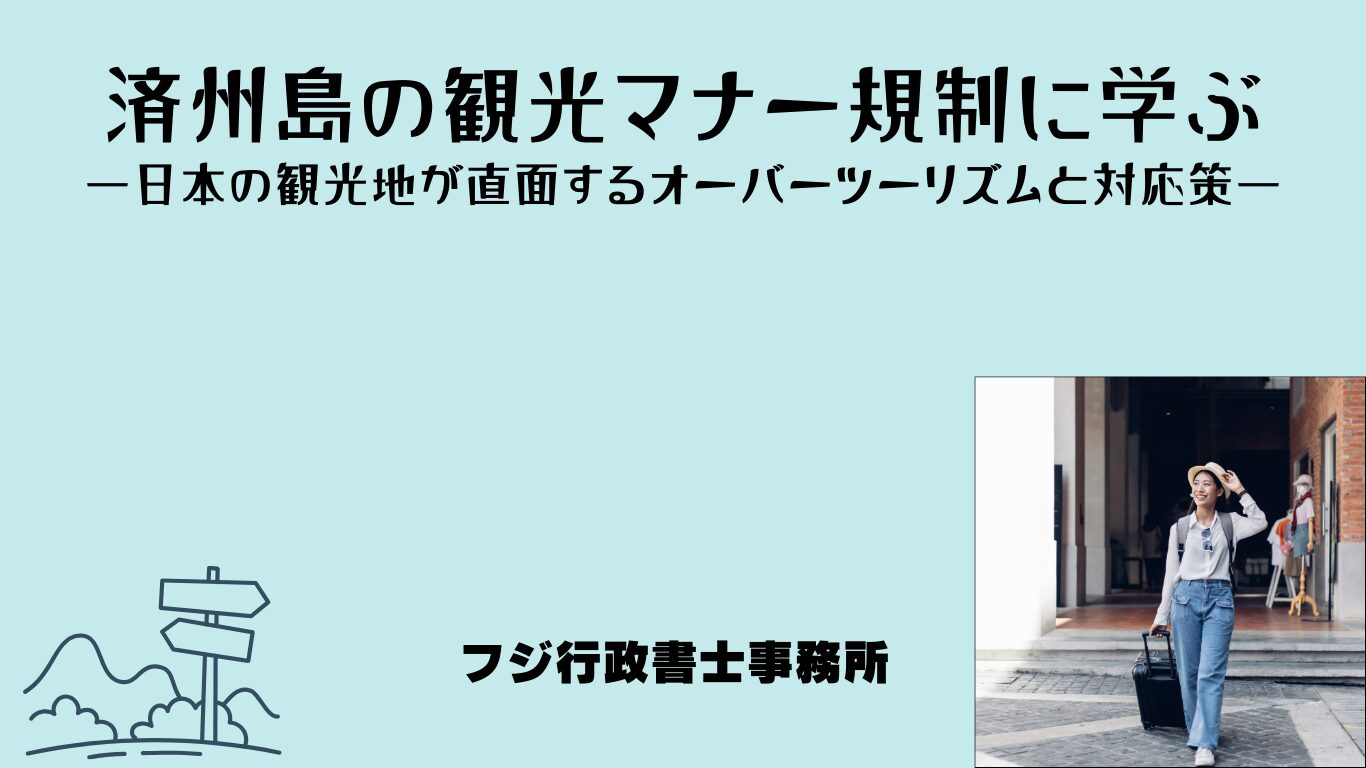済州島の観光マナー規制と背景にある事情
韓国の済州島が外国人観光客に対し、マナーを守るよう求める多言語ガイドを発行したというニュースは、多くの人に驚きをもって受け止められました。済州島は「韓国のハワイ」と呼ばれる人気の観光地であり、青い海や茶畑、さらには漢拏山の雄大な自然が観光の目玉となっています。しかし、観光客の急増とともに、迷惑行為やマナー違反も目立つようになり、地域住民や行政が問題視するようになりました。
実際に、昨年済州島を訪れた観光客は1300万人を超え、ソウルからの航空路線は世界で最も利用者数の多い路線とされています。新型コロナウイルスのパンデミック収束後には、外国人観光客が2021年の約4万8千人から2024年には190万人へと急増しました。こうした現実が背景にあり、観光協会は行動規範を多言語で示し、軽微な違反には警察が直接ガイドを配布する体制を整えました。再三の違反には最大20万ウォンの罰金が科せられる仕組みです。
ここでは、このニュースを出発点として、済州島の規制が「保守的な国だから」生じたのか、それとも観光地が直面する普遍的な課題なのかを整理し、日本との比較も交えて考えてみたいと思います。
保守的な価値観と現実的な事情
韓国社会には儒教的価値観が根強く残っており、公共の秩序や礼儀を重んじる傾向があります。観光客に対しても「決められたルールを守ってほしい」「周囲に迷惑をかけないでほしい」という集団志向が強く、その意味でマナー違反に敏感であることは確かです。済州島で今回のような多言語ガイドを警察が配布する仕組みは、そうした文化的背景を反映していると言えるでしょう。
しかし、それだけでは十分に説明できません。観光客の急増によって、島のインフラや環境が限界に達していることが現実的な大きな要因です。ゴミの放置、自然保護区での不適切な行動、交通違反などが目立つようになり、住民の不満が強まっていました。観光資源を守らなければ観光そのものが成り立たなくなるという危機感から、実務的な対策としての規制が導入されたのです。
さらに、世界の他の観光地と同様に「観光公害」への対応が国際的な課題となっている点も見逃せません。イタリアのベネチアでは日帰り観光客への入場料制度が始まり、インドネシアのバリ島では神聖な場所での不適切行為に国外退去処分が科されることもあります。京都では舞妓の無断撮影禁止や路地への立ち入り制限が導入されています。つまり、済州島の取り組みは、世界的に見れば特別に保守的というよりも、むしろ普遍的な流れの一環と考えられます。
日本の観光地が直面する課題
日本も同様に、観光客の急増による問題を抱えています。京都では観光客が路地に殺到し住民生活に支障が出ているため、私道への立ち入り制限が設けられました。富士山では登山者の急増によってゴミや渋滞が深刻化し、入山料や人数制限が導入されました。鎌倉や金沢といった古都でも、観光客が生活道路を占拠する状況が続き、地元住民の不満が高まっています。
ただし、日本は規制の方法に特徴があります。韓国が警察によるガイド配布と罰金制度という「即時性」を重視するのに対し、日本は「お願い」や「啓発」にとどまる場合が多いのです。背景には「お客様は神様です」という商習慣があり、客に不快感を与えないことが最優先される文化があります。迷惑行為に対しても正面から取り締まるより、ポスターや映像で呼びかける方法が選ばれる傾向があります。
しかし近年はその限界が明らかになりつつあります。富士山の登山規制のように、罰則や制限を伴う制度が導入される例が出てきています。京都でも条例による法的な立ち入り禁止が検討されており、従来の「お願いベース」から「ルールと罰則」への転換が進み始めています。これは、住民の暮らしを守るために不可避の動きだと言えます。
加えて、観光産業に依存する地域が増えていることも重要です。地方経済の衰退が進む中、観光は数少ない成長分野であり、その維持には住民と観光客のバランスが欠かせません。観光客を無条件に歓迎する時代から、共生のルールを明確にする時代へとシフトしつつあるのです。
罰則や退去という方向性
観光客のマナー違反に対する対応は、時間をかけて調査するハラスメント対応のような仕組みでは限界があります。現場で即時に処理できなければ、被害が拡大し、住民の不満も増幅してしまいます。済州島が採用した方式は、軽微な違反では警察が注意し、それでも繰り返す場合は罰金を科すという「即時性」のある仕組みでした。これは、長期的な手続きに頼らずに現場で解決するための現実的な工夫です。
日本では、退去強制のような措置は観光マナー違反には直結していません。ただし、危険行為や条例違反が確認されれば罰金や退去を命じられることはありますし、極端な場合には入管法の観点から退去強制につながる可能性もあります。ただし、それはあくまでも最後の手段であり、観光客一般に適用されるものではありません。
しかし今後、日本でもオーバーツーリズムが深刻化すれば、即時に注意や罰則、退去命令を行う仕組みが求められる可能性があります。住民の暮らしと観光産業の両立のためには、強制力を伴うルール化に踏み出さざるを得ないでしょう。
同時に、単なる罰則だけではなく「どうすれば観光客が気持ちよくルールを守れるか」という工夫も不可欠です。多言語の案内やアプリを通じた情報提供、地域住民との交流イベントなど、前向きな取り組みが併せて必要になります。観光客が「押し付けられた規制」と感じるのではなく「安心して楽しむためのルール」と受け止められるように設計されることが理想です。罰則と啓蒙、規制と歓迎、この二つのバランスをどう取るかが、日本の観光地がこれから直面する大きな課題になるでしょう。
以上のように整理すると、済州島の規制は「保守的だから」ではなく、観光地が持続可能性を保つための必然的な対応であることがわかります。そして日本もまた、これまでの「お客様は神様」という文化を背景に規制を避けてきましたが、観光客の増加に伴って従来のやり方では立ち行かなくなってきています。観光と地域社会の共生を実現するために、今後は韓国に近い即時的かつ明確なルール作りが不可避になると考えられます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。