タイ政府による短期課程ビザ規制強化の背景と狙い
タイ政府は2025年5月14日から、外国人留学生を対象とした短期課程(Non-degreeプログラム)の学生ビザ規制を大幅に強化しました。背景にあるのは、不正就労の温床となっていた短期課程を利用した滞在形態の問題です。これまで「学生」という名目で実際は働きに来ていた人々が多く存在し、社会的な課題となっていました。大学や語学学校などの教育機関は、今後は入国管理局へ学生の在籍・出席・学習状況を定期的に報告する義務を負い、違反すれば学生ビザの取り消しに直結します。すでに約1万人規模のビザが取り消されており、各方面に大きな衝撃を与えています。
この動きはタイ国内だけでなく国際的にも注目されています。なぜなら「留学生ビザを不正に利用して実際は働く」という問題は、タイに限らず日本を含む多くの国で共通する課題だからです。今回の規制は、タイがようやく国際的な水準に追いつこうとしている取り組みだと評価する見方もあります。
短期課程ビザが不正利用されてきた理由
まず押さえておきたいのは、なぜ短期課程の学生ビザが不正利用の温床となってきたのかという点です。
ひとつめの理由は、就労ビザよりも取得しやすいことです。本来、就労ビザを得るには雇用主の保証や一定の給与水準、専門性のある職種などの条件を満たさなければなりません。しかし学生ビザは比較的取得が容易であり、教育機関に在籍していることさえ証明できれば発給されることから、本当の目的が「働くため」であっても「留学」という名目で入国できてしまいました。
ふたつめは、出席義務や学習実態の曖昧さです。語学学校や短期課程は大学や大学院ほど厳格に管理されていません。出席率のチェックが甘く、授業にほとんど出席しなくても在籍証明さえあればビザ更新が可能なケースがありました。そのため、実際には働きながら「学生」という肩書きだけを利用する人々が増えてしまったのです。
さらに、低コストで長期滞在できることも大きな要因です。短期課程の学費は大学課程に比べて安価で、授業時間も少なく負担が軽いため、最低限のコストで「合法的な滞在資格」を手に入れられます。この構造が、実際にはフルタイム労働をしながら滞在する不正利用を助長しました。
加えて、労働市場での需要も背景にあります。観光業やサービス業、製造業など、タイ国内では低賃金で働ける労働力が求められており、雇用側も「学生」を事実上の労働者として活用していた実態があります。最後に、仲介ブローカーの存在も見逃せません。「学生ビザで簡単に滞在できる」と宣伝して外国人を集める業者がおり、当人は「合法」と信じて来ても実際には不正就労だったというケースも発生しました。
こうした要因が重なり、短期課程ビザは不正利用の代表的な抜け道となってしまったのです。
不正利用が多い国籍と日本の制度との比較
タイの報道や移民局関係者の話によれば、南アジアやアフリカからの学生が目立つとされています。バングラデシュ、パキスタン、インドなどから来た人々は、工場や飲食店で働くために短期課程を利用する例が多かったといわれます。アフリカ諸国からの学生も、実際には学業より就労目的で入国するケースがありました。また、ラオスやカンボジア、ミャンマーといった近隣国の人々も、「学生」として入国して出稼ぎをすることがありました。母国での雇用機会不足や収入格差が、こうした行動を後押ししています。
一方、日本の留学生ビザ制度はタイよりもはるかに厳格です。日本では出席率や学習進捗が細かく管理され、出席率が7割を切ると更新が難しくなります。アルバイトは「資格外活動許可」で週28時間以内に制限され、違反すれば退学やビザ取消となります。さらに入管庁と学校が連携して出席率をチェックし、マイナンバーとも連動する在留管理が進んでいます。
これに対して、タイの短期課程は長らく出席管理が緩く、形式的な在籍証明が重視されるのみで、実際の学業状況には目が行き届いていませんでした。そのため、日本に比べて「学ぶふりをして実際は働く」という利用がはるかに容易だったのです。今回の規制強化によって、タイは日本型の管理体制に近づこうとしています。
つまり、不正利用が多かったのは経済的に困難な国々からの人々であり、日本と比べて監視が甘い制度がその温床になっていたといえます。ここには、世界各国が共通して抱える「留学生ビザの労働利用」という課題が浮き彫りになっています。
規制強化がもたらす教育機関・学生・産業界への影響
今回の規制強化は、教育機関・学生・産業界それぞれに大きな変化をもたらします。
教育機関にとっては、学生情報を入管へ定期報告する義務が課され、出席管理システムの導入や人員配置など管理コストが増えます。真面目に教育を行っている学校にとっては「制度の健全化」としてプラスに働きますが、不正に加担してきた学校は摘発や閉鎖のリスクが高まります。結果として、「簡単に滞在できるから」と学生を集めていた学校は淘汰され、教育目的の留学生を受け入れる健全な学校が残る流れになるでしょう。
学生にとっては、不正利用者が減ることで安心して学べる環境が整います。しかし、これまで実質的にフルタイムで働いていた学生は生活が苦しくなり、経済的に厳しい層には滞在のハードルが高まります。出席率が低いと即ビザ取消になるため、怠学や働く目的での留学は難しくなり、結果として「本当に学びたい学生」だけが残る環境になります。
産業界においては、観光業やサービス業、製造業などで安価な労働力を学生ビザ経由で確保していた部分が縮小します。そのため、外国人労働者受け入れ制度(就労ビザ、技能実習、特定技能など)を活用する方向へシフトせざるを得なくなります。短期的には人手不足が悪化する可能性がありますが、長期的には合法的かつ透明性のある雇用へと移行することになり、企業の信用改善につながるでしょう。
こうして教育機関は健全化と淘汰の分岐点に立ち、学生は本当に学ぶ人だけが残り、産業界は安価な労働力を失って正規制度に頼る方向へ進むことになります。短期的には混乱が避けられないものの、中長期的には教育と労働の境界が明確になり、制度の透明性が向上することになるのです。これはタイだけでなく、日本を含む多くの国が直面する共通の課題であり、今後アジア各国がどのように留学生ビザを管理していくかを考えるうえでも重要な動きだといえるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
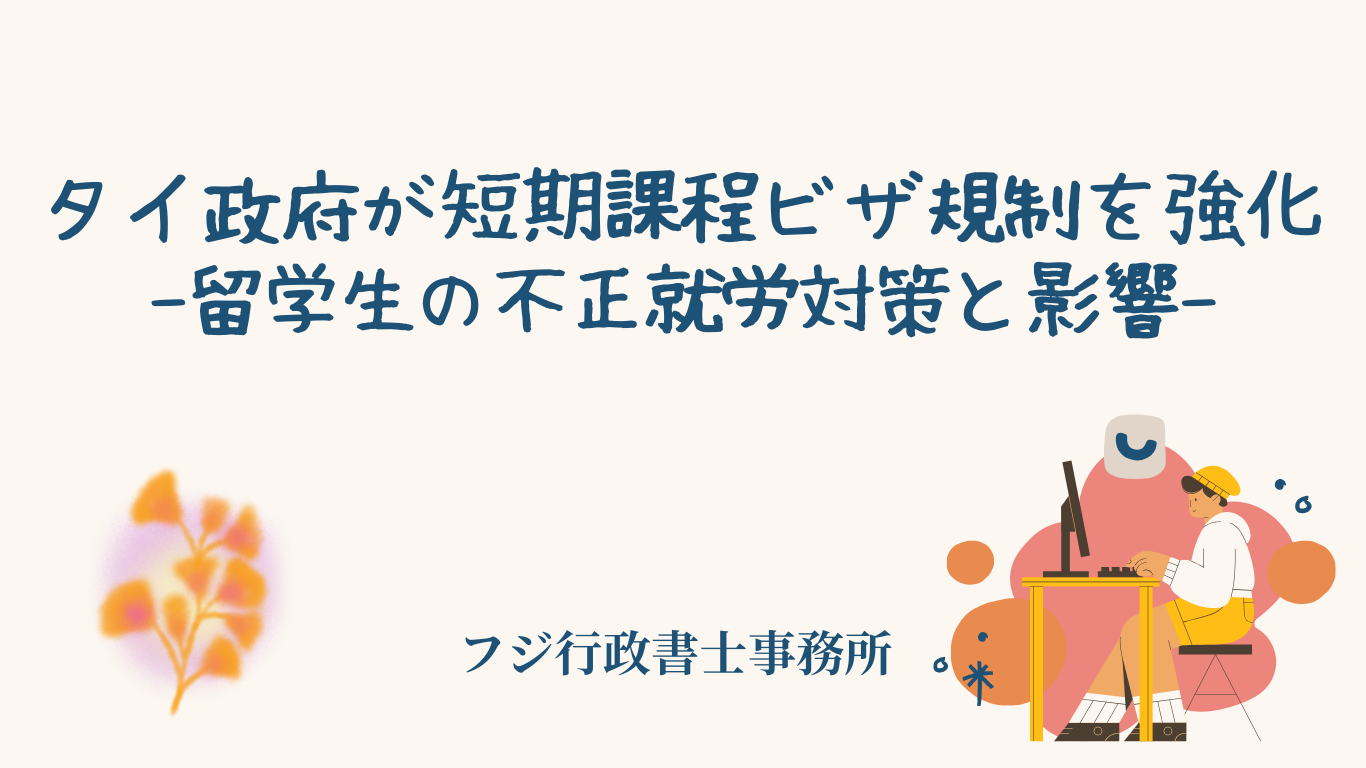
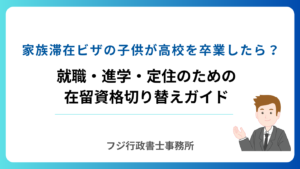







コメント