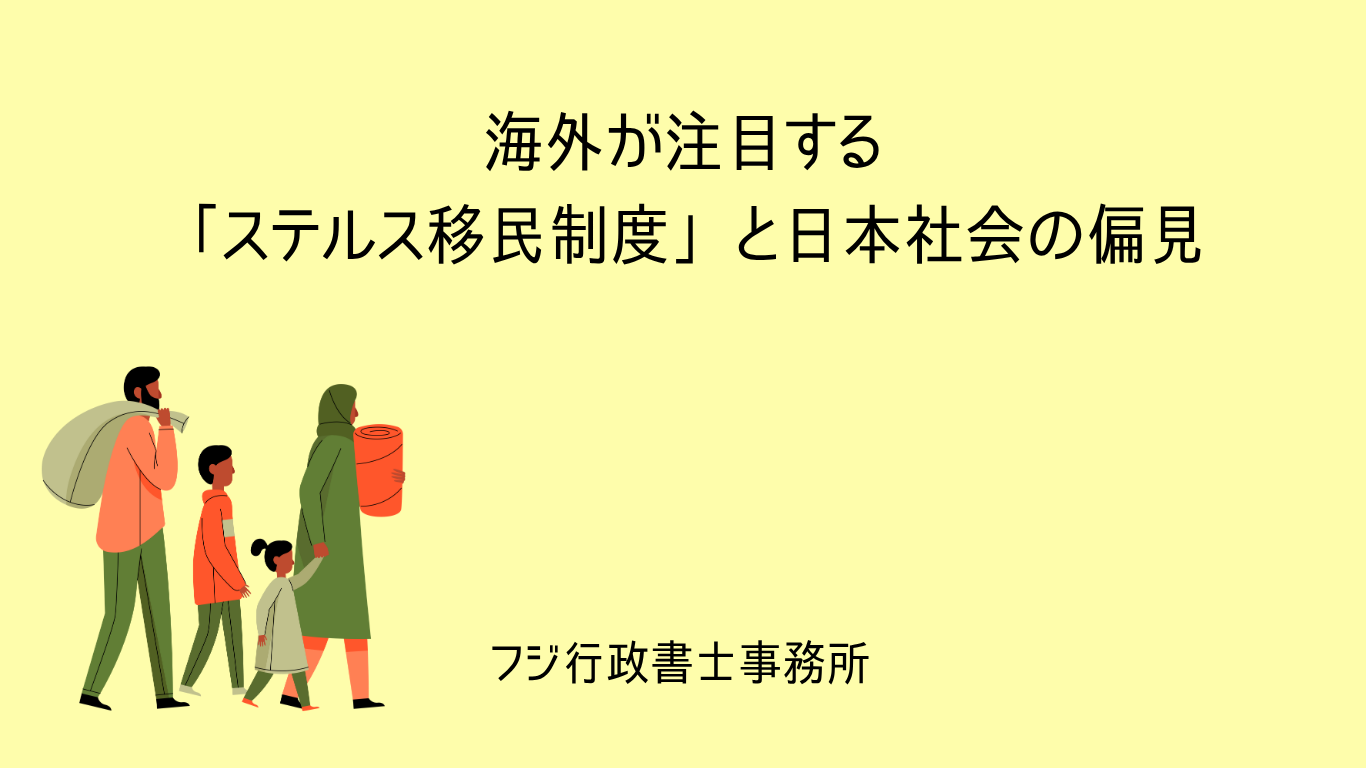海外報道が注目する「移民観」と日本の現実
近年、海外の複数のメディアが、日本社会における外国人・移民に対する固定的なイメージや制度のあり方を取り上げています。多くの日本人が、移民を「安価な労働力」「日本語を話さない」「子どもが学校を辞めがち」「治安を悪化させる」などと結びつけて見ている傾向があると指摘されています。こうしたイメージは必ずしも統計や実態に基づいたものではなく、SNSや一部メディアの論調によって増幅されることで、社会全体に広がっていく構図が浮き彫りになっています。
あわせて、海外では日本政府の移民受け入れの仕組みについて「ステルス移民制度」と呼ぶ見方も広がっています。これは、表向きは「移民政策を取らない」としながら、実際には技能実習や特定技能などの制度を通じて多くの外国人労働者を受け入れているという構造を指します。しかし十分な支援や生活基盤の整備が伴わないため、外国人側の孤立や、地域住民の側の誤解・摩擦を生む温床になっているとされています。
「ステルス移民制度」の構造と実務上のズレ
行政書士として在留資格や入管手続きの現場に携わっていると、この「制度と現実のズレ」は日常的に感じられます。例えば、技能実習や特定技能の在留資格では、日本語能力や受け入れ体制が形式的に整っているように見えても、実際には職場や地域で十分なサポートが行き届いていないケースが少なくありません。企業側も、外国人を受け入れるための内部体制や、地域社会との橋渡しの仕組みを持たないまま採用を進めていることがあります。
その結果、外国人労働者は職場以外で孤立しやすく、生活情報の不足や文化的な壁が偏見を生む原因になることがあります。一方、地域住民の側も制度の背景を理解しないまま「外国人が急に増えた」と感じ、不安や警戒感を募らせる場面があります。政府が受け入れを進めながらも、統合政策を十分に示していない現状が、こうした状況をさらに複雑にしています。
地域で実感する摩擦と共生の課題
大阪府箕面市では、ここ数年で留学生や技能実習生、特定技能で働く人々の姿が身近になってきました。学校や地域イベントでは外国人家庭が参加する姿が増える一方で、言語や文化の違いから行政情報が伝わらなかったり、支援制度を十分に活用できていないケースが見受けられます。
例えば、児童手当や扶養控除の申請、在留資格変更の手続きなどは、情報が届かなければ期限を逃したり誤った申請をしてしまうリスクがあります。こうした「制度と生活のギャップ」を埋める役割は、地方自治体や支援団体だけでなく、行政書士などの専門家にも求められています。現場で直接相談を受ける立場だからこそ、外国人と地域社会の接点が不足している現実がよく見えてきます。
専門家として見える今後の方向性
海外の報道が指摘する「偏見」や「ステルス移民制度」は、単なる国際的な批判ではなく、日本の制度設計と地域社会の課題を映し出しています。今後は、受け入れ政策をよりオープンに議論し、言語支援や生活支援を含めた統合的な仕組みを整えることが欠かせません。
現場の行政書士としても、在留資格の手続きを代行するだけでなく、支援制度や生活情報を丁寧に伝え、地域と外国人をつなぐ役割を果たしていくことがますます重要になると感じています。偏見を減らし、相互理解を進めることが、制度を「ステルス」から「共生」へと転換する第一歩になるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。