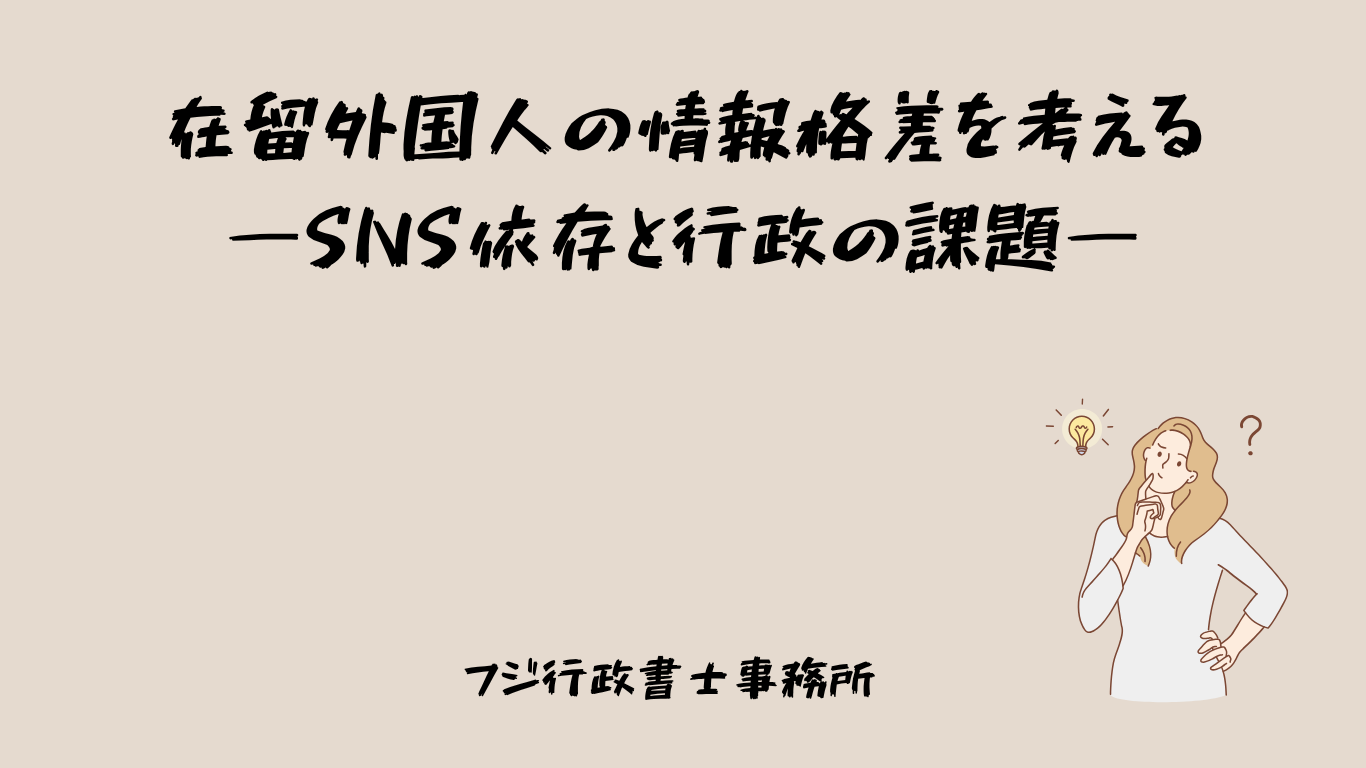情報はあるのに届かない現実
日本に住む外国人は年々増加しています。日本には学びのために来る人、働きに来る人、そして家族と一緒に暮らすために移住する人など、さまざまな背景を持つ外国人が暮らしています。彼らに共通しているのは、日本で生活するために多くの情報を必要とするということです。役所での手続き、病院の利用、子どもの学校や教育、税金や保険の仕組み、仕事探し――これらの情報はすでに日本社会の中に存在していますが、必ずしも外国人に届いているとは限りません。情報自体は豊富にあるのに、言語や理解の壁によって「アクセスできない状態」が生じているのです。これこそが「情報格差」の問題です。
日本語力の差とSNS依存の現実
情報格差が生まれる背景のひとつに、日本語力の差があります。日本語をある程度理解できる人は公式のサイトや窓口で情報を入手できますが、十分に読み書きできない人は、たとえ必要な情報が公開されていても理解できません。検索キーワードを思いつけない、難しい専門用語に引っかかる、長文の案内を最後まで読み切れない――そうした小さな壁が積み重なり、最終的に「情報を探すこと自体を諦める」という状況を生み出します。
そのとき頼りになるのが、SNSや同国出身者のコミュニティです。母語でのやり取りが可能なSNSは、外国人にとって安心感があり、気軽に情報を得られる便利な手段です。実際に経験した人の体験談や口コミは具体的で参考になり、リアルタイム性も高いというメリットがあります。しかし一方で、SNSや口コミは必ずしも正確とは限りません。「税金を払わなくても問題ない」「在留資格は自動で延長される」といった誤解が広まり、それを信じた人がトラブルに巻き込まれるケースも存在します。誤った情報を信じてしまうことは、生活基盤そのものを揺るがしかねない深刻なリスクなのです。
行政の限界と求められる対応
行政の情報発信には正確さという強みがありますが、それにも限界があります。公式な案内はどうしても専門的で硬い文章になりやすく、日本語に不慣れな人にとって理解が難しいものです。多言語化の取り組みは広がりつつあるものの、対応言語が限られていたり、翻訳が更新されるまでに時間がかかったりすることが多く、「公式情報はあるのに使いにくい」と感じられてしまいます。つまり、行政の努力が必ずしも外国人に届いているとは言い切れないのです。
こうした状況に対しては、単純に「やさしい日本語を使えばよい」「翻訳を増やせばよい」といった対応だけでは不十分です。現実に即した具体的な仕組みが求められています。情報を探す負担を減らすプッシュ型の配信、地域に根ざした信頼できる仲介者の活用、SNS上の誤情報への即時対応、専門家へのアクセス機会の拡充、さらに図解や動画といった言語に依存しない情報提供の工夫――これらが同時に進められてこそ、情報格差を縮めることができます。
多文化共生に向けた第一歩
情報格差を「日本語ができないから仕方がない」と片付けてしまうことは、社会に不平等を生むことにつながります。情報にアクセスできないことは制度を利用できないことに直結し、生活や権利の不公平を引き起こします。放置すれば不満や不信感が積み重なり、地域の共生にも悪影響を及ぼしかねません。
在留外国人にとって情報は生活の基盤です。正確な情報にたどり着けることは、安心して暮らすための最低条件とも言えます。そしてそれは外国人だけでなく、日本社会全体の安定や発展にもつながります。SNSの便利さと公式情報の信頼性、それぞれの特性を生かしながら、誤解を防ぎ、正しい情報を誰にでも届く形で提供する努力が求められています。情報格差を縮めることは、多文化共生を現実のものとするための第一歩なのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。